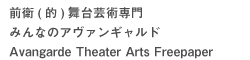|

©Mariko Matsubayashi
この2年の間にサルトルの長篇戯曲が若手演出家によって相次いで上演された。また最近はサルトルの伝記も邦訳出版されている。その書評に、サルトルのような<全体的知識人>は昨今の反知性的時代には出現しにくいと書かれていた。
日暮里d-倉庫の「現代劇作家シリーズ」は5回目の今年、そのサルトルの『出口なし』を取り上げた。このシリーズは毎年一人の作家の一つの作品を選んで10団体に競演させるというユニークな催しだ。J-P・サルトルは哲学・文学・政治その他の幅広い分野で活動した以外に、ボーヴォワールとの契約結婚でも世間の耳目を集め、60年代から70年代にかけて日本の知識人のアイドル的存在だったと記憶している。だが1980年に死去したあとの世界秩序の激変で、その存在はすっかり忘れられてしまった感じだった。
『出口なし』の初演は1944年5月、パリ解放直前のヴィユ・コロンビエ劇場。地獄に堕ちた一人の男と二人の女が密室で果てしない関係性の葛藤を繰り返す、というのがその内容だ。フェスティバルで「おや?」と思ったのは、素足のパフォーマーが多かったことだ。地獄だから素足?戯曲の冒頭に「第二帝政式サロン」というト書きがあり、のっけから地獄のイメージが覆されるのに。そうは言っても男女三人はみな死者で、劇が進むにつれて夫々が地獄へ堕ちた理由も明らかにされて行く。だがその一方で、登場人物たちは互いの関係を探り合い、中の一人(聡明な女・イネス)が、わたしたちはお互いにとっての鬼だと言う。(サルトルには「地獄とは他人のことだ」という言葉もある。)するとこの地獄は、必ずしも<あの世>ではないのかもしれない。
「IDIOT SAVANT」はこれに一つの解答を与えていた。前半はパフォーマーによる身体表現で、超絶跳躍技術を持った三人のパフォーマーが宙高く飛び上がっては裸舞台にドタンと落下する動作を繰り返す。これは地獄の表象だろう。後半はサルトル、ボーヴォワール、そのどちらかの愛人と思しき人物たちが赤い糸で三角関係の表象を繰り広げる。これまた生き地獄だ。なんせ理想のカップル像は二人の死後に砕け散ったのだから。
「大人少年」は空間を上下二つに分け、上がこの世で下が地獄という一見単純な構成ながら、この世の人たちに地獄堕ちの三人の噂話をさせる。それによって他者は鬼という主題を戯曲とは別の形ながら(すごく日本的に)シンプルに表現していたと思う。
『出口なし』はサルトル哲学の芸術化だと言われている。三人が密室に閉じ込められる状況は、存在論を芸術に接続させる恰好の設定には違いない。この地獄には鏡がない。もう一人の女エステルは、鏡に映った自分の姿を見ないと自分が誰なのか分からなくなる。イネスが「あたしが鏡になってあげましょうか?」と提案するが、他人の眼に映った自分を自分とは認識できないと言って断る。これじゃあまるで統合失調症状態だが、サルトルに言わせれば、本来は対自=対他的存在であるはずの人間の自己同一性の危機である。鏡については各グループとも慎重かつ丁寧に扱っていたが、戯曲の言葉を超えるほどの表現には遭遇しなかった。ただ獣の仕業は、サルトルが何ぼの者じゃという方法論(?)を持っているのか、直観的に鏡の意味を捕えて自由に構成した舞台が新鮮だった。考えた末の構成だったらごめんなさい。
今年は新しい試みとしてフェスティバルの最後にシンポジウムの日が設けられた。10団体の代表が舞台上で長時間お互いの作品の批評をし合った。反知性的=商業主義的演劇がはびこる中で、このフェスティバルは貴重だ。

©bozzo
|