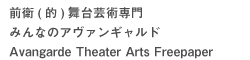|
脱領域的に手法が混じり合い、表現が多様化する一方、前衛という言葉が死語に響くほどに表現が常套化し、アクチュアルな切れ味を示す舞台が少なくなっている。そんな中で、「前衛」という旗印を掲げ、実験的な挑戦を続けているのが真壁茂夫の率いるOM-2(旧黄色舞伎団)である。視覚性に優れたその独特の舞台は、台本を排除して言葉による解釈を拒否し、舞台の時空間を生きる身体の発するものを重視している。即興の練習の積み重ねで初めて成立する表現にこそ肉体(存在)の真実が宿るとして、観客と共有する時空間に生まれる共振性を追究している。
第9作目となる新作の『OPUS No.9』を観た。(3月20日、日暮里サニーホール)今回の作品は、20世紀アメリカ演劇の名作、アーサー・ミラーの『セールスマンの死』を発想の原点としているが、真壁自身がプログラムで述べているように、物語をなぞるものではなく、素材から触発された感情や思考を演出家独自の手法で舞台上にイメージとして立ち上げている。

©塚田洋一
異色の構成で、激しく打ち鳴らされるドラム、身体の部分を打つプリミティブな打撃音(ボディ・パーカッション)、タップ、ヴォイシングなど、全編にわたり音とリズムの探究を行い、多様な音と律動を生きる身体の動きや表情を融合して原作の扱う人間のあり様を感得させようとする試みである。(構成・演出 真壁茂夫、音楽監督・作曲が小田z善久)
日暮里サニーホールの空間を二つに分け、仮設の舞台を設えた二部構成の舞台。一部では、一段高くなった細長い舞台上にシンポジウム風に机を並べ、4人のパフォーマーによる指、拳、肘などで机を打つパフォーマンスが繰り広げられる。コート姿の男(佐々木敦)が鞄を下げて登場し、上着を脱いでパーカッションのパフォーマンスに加わる。主人公であるセールスマンの父親役と思しき男の造形や遺産や相続のことを語る男女の断片的な台詞によって、原作で倒叙の形で示される父の死に直面した家族のドラマをうっすらと立ち上げる。
パフォーマーの身体の一部や顔が映しだされる映像とその場で瞬時に生みだされる音などによる多重構造のパフォーマンスは、台本に基づく舞台とは異なる臨場感を醸成している。俳優たちの身体は既定の役柄を演ずるのではなく、パーカッションの演奏のなかで空間に広がる音と律動の共鳴体としてむしろ物質的にアクチュアルな説得力を発揮している。
後半では、場所を移動し対面式に演技が続く。白一色の舞台に箱が置かれ、そこから手や顔をのぞかせて演技したり、箱の上や後方の舞台でパフォーマー達がタップを踏んだりする。タップ音は軽快というより重く不揃いで、耳障りのまま観客の感覚を襲ってくる。
陰影の濃い照明を用いて首だけ箱から覗かせたり、腕の部分を演技させたりする手法は、サミュエル・ベケットが試みた実験的なミニマル演出をも想起させた。

©塚田洋一
原作は、老いたセールスマンの父親が時代に取り残され、自死による保険金でローンを完済して家族を救うという悲劇。競争社会の闘いに敗れた父親と家族の悲哀をテーマとしており、社会の底辺で抑圧される庶民の姿は今日の現実をも照射する。父親役を演じる怪優、佐々木敦の強烈な存在感が際立つ。終幕では精神的に瓦解し、自死を選ぶ男の姿を不気味な持ち味を活かして熱く造形した。
ただ、意表をつく音源を含めた多様な音と動きを呼応させる異色な演出は面白いものの、音楽性もしくは音響効果にさらに工夫が求められる。起爆力のある音創りと呼ぶには中途半端なのだ。テーマ性と具体的な表現の間に乖離があり、それが観客の感性との共振を妨げたように思われる。前半は、導入部として観客の思考の磁場を築くのに成功していたものの、場を移した後半では要素が散漫なままインパクトを欠いた。例えば、各人各様に踏むタップの音と律動感は、期待通りの効果を発揮していない。機能性に流れた身体表現が表層に留まり、深部へと浸透しないのだ。不揃いで、時に耳障りなタップ音にしても、異なる個人が構成する社会そのものの軋みや摩擦には聞こえてこない。観る側に負荷を与える仕掛けだとしても、観客の感性と絡み、コミュニケートする音楽の緻密な組み立てが必要だろう。
社会の底辺に生きる庶民の悲哀を描いたミラーの名作が呈示するテーマは、新資本主義が生み出す現代社会の矛盾と確実に響きあっている。さらに練り上げて、改めての挑戦に期待したい。
|