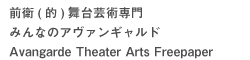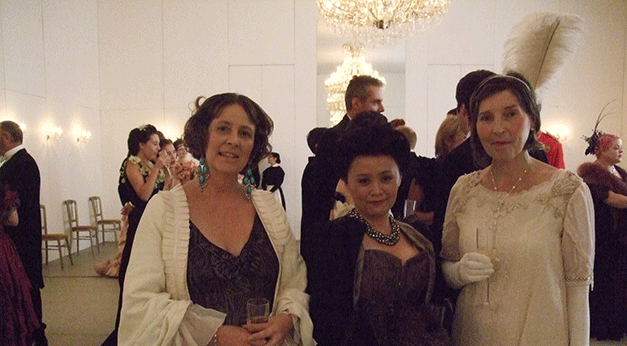「イマーシブ・シアターの到来が意味するもの」
中山夏織
|
|
中山夏織:NPO法人シアタープランニングネットワーク代表。アートマネジメントや文化政策等を教えながら、様々な国際交流やドラマ教育、人材育成プロジェクトに携わる。近年、障害児のためのアウトリーチ型演劇鑑賞「ホスピタルシアタープロジェクト」を主催。主な著書に『演劇と社会―英国演劇社会史』他、主な翻訳に『応用ドラマ―演劇の贈りもの』他、戯曲の翻訳に『ハンナとハンナ』『カラムとセフィーの物語』『宮殿のモンスター』他。2012年より日本芸術文化振興会プログラムオフィサー。 |

『The Salon Project』
1950年代にはじまる小劇場運動は、英国では「オルタナティブ・シアター運動」として呼ばれる。非常に豊かな実験性と政治的な側面をもつ運動だったものの、日本と異なるのは、多くの優れた人材を輩出したが、ついぞ「オルタナティブ」の冠から逃れられなかったことだ。英国演劇の主流は、ウエストエンドの商業演劇や、それなりにコンテンポラリーな装いをもちながらも、シェークスピアに代表される「トラディショナル」、あるいは、自然主義の「コンサバティブ」の枠のなかにあり続けてきた。そのメインのターゲットは、教育のある中高年の白人である。
さらに、公的助成の考え方も、実験的なものを好まず、いわゆる質の高い「エスタブリッシュト」を支えることを旨としてきた。もちろん、それだけが理由ではないが、どこか新しいものを容易には受けいれない環境が強くあった。それが英国的なるものの主流であり、1999年の劇作家サラ・ケインSarah Kaneの夭逝も、多分に、その英国的なるものの犠牲だったのだと位置づけられる。実際、私がロンドンに留学していた90年代中ごろ、コンプリシテや、チーク・バイ・ジョエルが奮闘しながらも、多分に若い観客をひきつけるのに失敗していた。ある新聞が報じたのは、若い世代が演劇の宣伝からして「ダサい」「クールじゃない」と感じていたことだ。
しかし、世紀の変わり目あたりから、そして、9.11を経て、英国演劇の様相に少しばかり変化が訪れた。これまでオルタナティブ、あるいはどこかキワモノと扱われてきたパフォーマンスの要素を強く持った新しいタイプの「インタラクティブ・シアター」の登場である。そもそもインタラクティブ・シアターは学校巡演を旨とした、シアター・イン・エデュケーションの参加のあり方に一つのルーツを見いだせるが、学校という一般に「見えない場所」での公演、教育という冠もあって、世間を惹きつけるものではなかった。
きっかけを生みだしたカンパニーが、2000年設立の芸術監督フェリックス・バレットFelix Barret率いる「パンチドランクPunchdrunk」であり、そして、いつの頃からか、彼らのような活動の総称として、「イマーシブ・シアター」という冠が付されるようになった。そして、大西洋をはさんだ英国と合衆国で、このイマーシブ・シアターを名乗るカンパニーが急速に増え、人気を博すようになった。イマーシブを名乗るカンパニーの主眼は、演劇をトラディショナルに、コンサバティブに縛りつけ続ける様々なコンベンションに挑むことにある。とりわけ、観客との関係性―契約のコンベンションを覆すことにある。
演劇ビジネスには様々なコンベンション―決まりごと―が存在する。演劇を学ぶのは、多分にこのコンベンションを知として、あるいは、身体として学ぶことから始まる。表現という記号と、演劇の「嘘」というコンベンションに取り囲まれ、私たちは創造とその提供という仕事に携わる。劇場という容器、前売り券や当日券といったチケットの販売方法、チラシや他の広報というビジネスも、様々なコンベンションで構成される。観客もまたそれを受けいれ、同時に守られる形で演劇に参画する。そこに助成機関や行政という異種のコンベンションも加わり、巨大な経済のシステムの中に、ささやかな演劇の「システム」が確立する。だが、一度確立してしまったシステムは、容易に変化を受けいれることはない。だから、ときに、激変する社会と、デジタルに生きる人々の暮らしとのあいだに大きな齟齬を生んでしまう。
21世紀生まれのイマーシブ・シアターが提起したのは、演劇ビジネスが当たり前としてきた「劇場の客席に座り、多くの場合、第4の壁となって、一方的に提供されるできあがった作品の傍観者としての観客」の否定だと整理できる。自明の理とされてきたことの多くを否定し、デジタル・テクノロジーとゲーム世代が求めるエキサイティングな演劇のあり方を探ることから模索がはじまり、次のような、ある種の「文法」が成立していった。
既存の劇場空間⇒ サイト・スペシフィック(あるコンテキストをもった特殊な空間)
固定の客席⇒ プロムナード/ウォーキング・ツアー(座っていられない)
第4の壁⇒ 舞台と客席の境界線を撤廃。
舞台装置・小道具 ⇒ インスタレーション/五感に訴える
一方的な作品の提供⇒ インタラクティブな関係性/シーンの展開順番
傍観者⇒ 参加。物語の一部・中核的存在になる
そして、ついには、パフォーマーたちが一人の観客と対峙する関係性までもが登場する。
『溺れる男―ハリウッドの神話The Drowned Man – A Hollywood Fable』
2013年6月から1年間にわたり、パンチドランクとロイヤルナショナルシアターとの共同製作により上演された『溺れた男-ハリウッドの神話』から、具体的に、この「文法」なるものを探ってみよう。
1.空間:
パディントン駅に隣接する、かつて郵便局のオフィスだった廃墟的空きビルが、架空のハリウッドの映画スタジオ「テンプル・スタジオ」として蘇った。巨大な4フロア全体を用い、それぞれ大小の部屋が、映画セットや化粧楽屋、近郊の町、砂漠等となり、それぞれが徹底したビジュアルで飾られる。インスタレーションとしての装置や小道具のディテールと美しさは圧巻。
2.観客:
仮面をつけて(強制。はずすと注意される)、その4フロアをひたすら自らの意思で彷徨い歩く。しかし、どのフロアから鑑賞するのかを観客は決められない(エレベーターで連れて行かれ、強制的に降ろされる)。それなりの勇気がなければ、動けなくもなる。
3.
一度の観劇で、必ずしも、全シーンが見られるわけではない。あらかじめ、地図が渡されるわけでもなく、自分で手探りしていく。
4.
第4の壁は一切存在せず、装置や小道具に触れることも可能。観客を蹴散らすように、パフォーマーは、演じ、踊りまくる。めちゃめちゃなまでに近接的。
5.物語:
映画スタジオのカップルと近郊の町のカップルの二つのナラティブが相互にミラーしながら展開。台詞からナラティブを理解するのではなく、小道具や場所から観客は物語を推測していく。(難しい過ぎるという批判から、途中から簡単なアウトラインが配られるようになったらしい)
6.一対一の対峙:
少し高額なプレミアム・チケットを購入した観客は、特別のエントランスから入場し、一度に、一組のみの特別なプロローグのシーンが提供される。
このように綴ると、少し知的で難解なディズニーランドか、幽霊屋敷なのじゃないかと揶揄もされるだろう。観客も決まった導線に従って歩くわけでなく、探求し、彷徨い歩くわけで、疲労もあれば、不安感、ストレスを募らせることもあるだろう。だが、肝心なことは、観客もまたリスクを負う契約を交わしたうえで、参加していることである。
アートマネジメントの視点からも実に興味深いものがある。もとより、英国には、日本のようなA4判のチラシをばらまくという習慣はない―長3封筒サイズにはいるカード・チラシが一般的だが、その郵送料は高くつく、エコじゃない、というわけで、21世紀に入ったころから、Eチラシが導入され始めた。劇場の場合は、シーズン・プログラムを作るが、年間1本、多くて2本しか創造しないパンチドランクのようなインディペンデントは、シーズン・プログラムを作る意味がない―といっても、『溺れた男』の場合、メインストリームの頂点ナショナルシアターが共同製作にはいっているから、自ずと、そのシーズン・プログラムには掲載された。それはさておき、これが重要なのではなく、パンチドランクの戦略は、あえて大々的な宣伝を避け、徹底してメールやSNSに集約したことにある。
幕が開けてから生じた現象は、観客が次の観客を呼ぶ―つまり口コミと、リピーターが続出したことである。チケットの価格は決して安いものはなく、むしろ高額なのだが、口コミとリピーターの続出がこれまで劇場に足を運ばなかった観客層を開拓し、予定以上のロングランを可能にした。
この背景には、観客は自分の体験を、他者に語らずにはいられない強い衝動がある。不安を体験したことも、むしろポジティブに働く。誰もが同じものを同時に体験したわけでもない決定的な事実が、体験者同士の対話につながる。リピーターが多いのは、謎解きを続けたくなるからだ。また、話を聞かされた者は、話を聞いた時点ですでにその体験の幕が開く。大々的な宣伝をしないほうが、かえって何か「シークレット」なものとして、心に訴えかけた。
YouTubeでこの作品の体験の感想を、15分以上にわたり一人嬉々として語り続ける女子学生の映像を見つけた。語らずにはいられない。語ることで体験がさらに深いものになる。これまでこんな強い衝動を引き起こす演劇体験があっただろうか? 生涯のうち、何度経験できるのだろうか? 一時的な流行で終わるかもしれないが、新たな観客を開拓し、新たな関係性を導きだしたことは否定しえない。
『サロン・プロジェクトThe Salon Project』
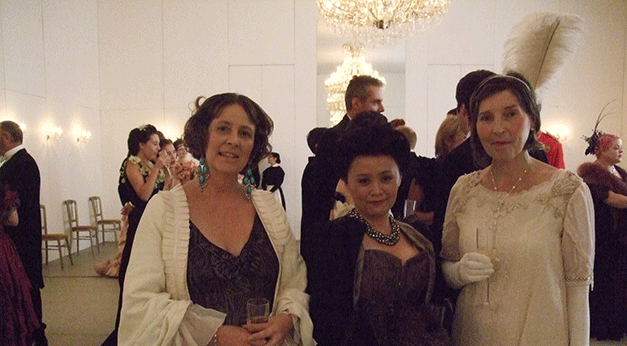
『The Salon Project』
劇団自体はこの作品を「イマーシブ・シアター」と呼びはしなかったが、たしかに「イマーシブ・シアター」と呼べる作品が、2011年10月、エディンバラのトラバース・シアターで初演された。デザイナーで演出家スチュアート・レイングStuart Laingが1998年に設立した「アンタイトルト・プロジェクト」というフリーランスの芸術家、プロデューサーたちの集団による『サロン・プロジェクト』である。もとよりレイングの活動は、視覚と体感に訴える演劇である以上にイベント的な要素で特徴づけられてきたが、このプロジェクトは究極的なまでの観客の参加を求めた。
チケット購入の段階で、観客は自らの身長、体重、バスト、ウエスト、ヒップ、靴の各サイズを申告する。劇場に指定された時間に到着すると、特設の衣裳部屋へ案内され、時代の衣裳を着せられるだけでなく、化粧、アクセサリー、ヘアメイクも施された後、19世紀末のパリの社交界のサロンを模した純白の空間へと導かれる…。観客、俳優、音楽家、スタッフ、そして批評家までもがその時代の衣裳をまとい、サロンを構築する。それだけなら時代物のテーマパークと大きくは変わらないだろう。だが、レイングが構築したサロンは、自分たちから一歩抜け出て架空のアイデンティティをもって、21世紀の今日と未来が直面する課題を、サロンの自由な空気のなかで考える体験の場へと転換された。音楽、美術、画像、レクチャーといった知的、かつ政治的、そしてプロボカティブな演劇的遊びの要素が加えられて、サロンは、一気にコンテンポラリー・アートの様相をも示す。ある瞬間、観客は自らの存在そのものがインスタレーションの一部となっていることに気づく。
ちなみに、『溺れる男』では観客による撮影は一切禁止されていたが、『サロン・プロジェクト』では観客も撮影が許された。また、オフィシャルな写真も、毎公演後、サイトで公開され、観客にダウンロードを許した。通常、オフィシャルな写真の使用は、アーティストら関係者にのみ許されるものだが、『サロン・プロジェクト』はすべて観客のものであると位置づけた。この英断(と呼ぶべきだろう)は、観客同士のあいだにコミュニティを生みだす効果をもたらした。観客はその写真を手にしながら、その体験を一生忘れることはない。
2つの『アルマ・メーターAlma Maters』
『サロン・プロジェクト』の初演された1年前の2010年11月、グラスゴーで「IETM-国際舞台芸術ミーティング」が開催された。市内30か所で、様々なショーケース・イベントや会議が展開された。ユニークだったのは、数多くのサイト・スペシフィック芸術イベントを含んでいたことだ。その中でもとりわけ評判を呼んだのが、スコットランドの歴史的デザイナーのレネ・マッキントッシュの設計・デザインで知られる「スコットランド・ストリート学校博物館」で繰り広げられた、二人の若い芸術監督が担う劇団フィッシュ&ゲームFish & Gamesの『アルマ・メーターAlma Mater』である。

『Alma Maters』
会場は、現在は博物館になっているが、もとは学校。いかにも学校の体裁とマッキントッシュのデザインが共存する空間である。観客は、約15分毎に一名ずつ、その空間に招かれる。手渡されたiPad上の映像と、ヘッドホンから流れる音楽に導かれて、その博物館の空間を歩いていく。ときに、立ち止まり、その「空間」が内包する物語を、映像の中に見る。目の前にある現実と、iPadのなかの映像―パフォーマーたちは映像の中に息づいている―が交錯するなか、観客は、若干の眩暈とともに時空を飛ぶ。
ふと、思うのは、その場にパフォーマーのいないパフォーマンスを「舞台芸術」と呼ぶのか、という抜本的な疑問とともに、ミュージアムでの体験を生きたものに変える演劇の力である。
この成功を受けて、助成機関スコットランド芸術評議会(当時)が、劇団に要望したのが、会場と素材が博物館そのものではツアーしえないので、このiPadシアターをツアーしうるものにすることだ。そして、翌年夏のエディンバラ・フェスティバルで、上演された『アルマ・メーター』は、学校の寮の7歳の少女の部屋を暗示する、ベッドの置かれた部屋-ハコ―の中で繰り広げられた。
観客は、一人ずつ、iPadとヘッドホンを装着し、狭いハコの中に案内され、映像と音楽により、7歳の少女の学校生活とその周辺のイメージを追体験するのである。狭い空間に一人閉じ込められ、スピリチュアルな側面をもつ映像と音楽に取り囲まれると、それなりに怖い体験ともなったらしい。
体験の質を問う
公演そのものの質の高さが求められるのはいうまでもない。しかし、観客一人ひとりにとっての体験の質は、これまでほとんど問われてこなかったのではないだろうか? アンケートに綴られるコメントは、観客の体験の本質をついているのか? また、観客はどれだけその公演の体験を覚えているのか? どのように? 劇場をでて、「面白かった」という一言を発した後、それ以上の何も覚えていないことに気づくことはないだろうか? 鑑賞という体験が、観客一人ひとりの生活を何らかの形で変えるものになるのか? もちろん、一過性や予定調和の娯楽としての演劇を否定するものではないが、イマーシブ・シアターの登場は、単に消費されるだけの作品を生産し続けてきた演劇ビジネスへの警鐘と思われてならないのだ。
|