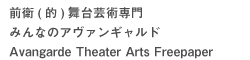舞台芸術/先進的役割について
小池博史(「小池博史ブリッジプロジェクト」主宰)
「パパ・タラフマラ」(1982年〜2012年)にて55作品制作。解散後「小池博史ブリッジプロジェクト」にて8作品。現在『マハーバーラタ』はアジア中のアーティストを巻き込んで展開中。約40カ国で公演。海外での創作は10本。つくば舞台芸術監督、国際交流基金特定寄附金審議委員を歴任。著書に『ロンググッドバイ』『からだのこえをきく』等。 |
 ©小池博史 ©小池博史
現在の日本の舞台について書くのは気が進まない。状況を詳しくは知らないという理由はあるが、それ以上に現状を直視すれば耳に優しい言葉は出て来そうもないからだ。日本は「世間」が幅を効かせる国だ。それがとても厄介な状況をもたらす。私は舞台界の「世間」とは距離を置いてきた。健全なあり方だと思うからだが、「世間」が支配する日本では「世間」と一体化しないのはどうにも厳しい、との前振りの下で書きたい。
さて、たまに舞台を日本で見に行くことはあるけれど、あまり感心はしない。「新しい」作品を制作しようと創作するのだろうが、いつか見たものが形を変えて出現しただけだったり、自己承認欲求によって作られた作品だったり、身体不在化による作品だったり、近視眼的な同意が得られそうな作品だったり、頭でっかちの、意味ばかりが見え過ぎる作品だったりで、もう少し根源的な部分にまで突っ込んでいく作品がないものかと思ってしまう。大きなビジョンが感じられないのである。だが、そんな作品群を新しい舞台だと信じ込もうとしている節がある。ひとつの流れが出てくると、面白がって流れに従い「新しさ」を持ち上げる、つまりみなで一所懸命、新しさ作りに励んでいるようにも見える。
批評は読まなくなってほぼ二十年にはなるか。当時、日本の批評は解説か分析がほとんどだった。解説は丁寧な自己流の説明に過ぎず、「分析」は批評家の勉強の成果+α程度の自己確認行為であって、批評とは呼べない。批評は元来そんな安易なものではないから、私は勝手に分析屋だと言っていた。元来、批評であるための最も重要な点は、批評自体が作品としての力を持つこと、つまり批評が詩性を伴った作品として成立しているかどうかが問われる点である。詩性探求は自己確認行為からは遠く、新たな境地を探り出すきわめて能動的な行為として作家の矜持が必須であり、それがあるからこそ、舞台創作者との対等な関係性が構築できる。作家が必死になって前に向かおうとするのだから、批評家に同程度の覚悟は必須である。それを知ったふうの分析屋に足を引っ張られたのでは叶わない。
歴史を見返せば、この国はどうにも気持ちの悪い状態を繰り返すのが好きなようだ。たとえば現在の立憲主義を屁とも思わぬ政治状況はどうだ。これに対して強い違和感を持ち、反対する人は多いだろう。しかしこの状況は政界のみではない。政治状況は社会の写し鏡である。つまり政治状況も舞台芸術状況も同じだということ。それなりに力のある舞台芸術界のある人物が「今は身体の不在化が普通になった。ならば、その身体を用いて舞台作品を作ればリアリティが出てくる」と言ったのを五年前直接耳にしたが、こんなパラドキシカルな言説がおかしいとも思われず、今も進行中である。
今の舞台芸術界がこうなったのと、人々の性向、社会状況、むろん政治は大きくリンクし、蛇行して絡み合いながら複合性を持って全体を作り出している。嫌になるほどの近視眼化が一般的になってきた。目の前の新規さを追いかけて、ひょいと飛びつく。しかし他のフィールドは見えても足元は見えない。だから政界は妙だと思いながら、一方、我がフィールドは健全だと思い込む。「私」は常に正しいのだ。なにも政界だけが奇形化しているのではなく、舞台芸術作品も奇形化した。けれどこの現象は日本ばかりではなく、次第に世界全体も奇形化しつつあるからさらに見えにくい。
 ©小池博史 ©小池博史
私は前衛的作品を作りたいとは思ったことはない。が、常に先頭には立とうとしてきた。しかし舞台は興行性が常に付きまとう。また同時代に評価されなければ後々は絶対に評価を受けない宿命がある。ゴッホや宮沢賢治のようにはいかないのである。だが芸術作品の創造を望めば、作家は遥かな過去と未来を同時に見据える気概を持ち、かつ芸術家である限り、一歩二歩先ではなく、遠く見たことのない世界の現出を望む。
昔、文化庁の役人が「文化庁は真ん中の真ん中が好きです」と言ったのを聞いた。文化庁なれど人それぞれだし、よくぞ正直に言ったものだと思ったが、その傾向は今も続いている。では、「真ん中」とはなにか。普通に考えれば「すでに評価の高い芸術」ほどの意味だろう。「すでに評価が高い」のと、常に先進的であろうとするのは意識の上では乖離する。評価の高さを守ろうとすれば、同じような作品制作を続け、「真ん中」入りして権力を持つのが良い。昔は前衛であっても守りに入れば保守化して頑なになる。また権力と芸術的精神は相反する。
文化は常に新しさと古さがせめぎ合って深度が増す。そしてその均衡のなかで市民の民度は上がるが、さて今、市民の民度は上がっただろうか。まったくそうは思えない。政治状況を取り巻く市民の態度を見れば一目瞭然だ。思考停止が一般化した。ならば民度は逆に低下し、強い芸術を受け入れる土壌は薄くなる。
十年前、ある美大で教えていたとき、女子学生が言ったことばが忘れられない。「私も母も、宣伝を十分行い観客が入る公演しか行かないんです。だから劇団四季が一番良いんです」と。一般大学生ではなく美大の学生が言ったのである。大衆受けする美術型商品に圧倒的に重きが置かれる時代になったのだと驚いた。劇団四季の価値は認めるが芸術ではない。なぜならほぼコピー商品だからで、コピーは芸術的精神からは遠い。それから約十年が経過した。惨状、甚だしく感じるがどうか。
芸術とはなにか。それは深淵を覗く行為だ。ただのおしゃれで楽しいものではない。だがそんな芸術を認識し落とし込むには民度の高さが強く要求される。でなければ芸術はクオリティを保てず、興行のための演目でしかなくなる。そして時代と寝て時代の一歩先を行く素敵な芸術、新しい芸術がもてはやされる。
舞台芸術の場合、先進的芸術創作を拒む最大の理由は、演劇や舞踊にジャンルが分かれて不思議とも思わないことだ。そしてその大きな原因は私たちの身体にある。頑なな身体が表層に留まって根源的身体性探求を拒む、その状態が心地よくなってしまうのである。ゆえにジャンルに安住して疑問を持たぬ。つまり今、最も求められるのは形の上での新しさなどではない。生命記憶を持って語り動く意識であり、そこからさまざまな要素を引っ張り出して、現在を語りつつ未来を見つめることだろう。表層にばかり捉われるから「不在化した身体を用いればリアルだ」というような、一見さも分かったふうに聞こえて、実は空疎なことばが漏れ出る。不在化した身体を用いる舞台はそもそもから舞台芸術に対して不敬でさえある。
私は世界中の多くの伝統芸能者と一緒に作品を作ってきた。彼らの身体は強い。一方、日本人の俳優はみっともない身体で平気である。が、見慣れればなんとも思わなくなる。むろん伝統芸能者は別だが、現代劇の俳優は身体が使えず、舞踊家は踊る身体しか持っていない。築地小劇場で小山内薫が「踊るな動け、歌うな語れ」と叫んだという伝説をそのまま守っているのが今の日本の演劇界であろう。舞踊界も似たようなもので、どこもかしこも西洋舞踊を追いかける。しかし元来、身体は文化背景があった上で多様であり最も身近な自然、小さな宇宙体と言ってよい。それを十全に、古代と繋がりつつ駆使する意識があってこそ新たな世界が作れる。
そして、舞台作品上で空間と時間をいかに作り出すか、その強い意識がなくては、舞台作品の深層などは見えては来ない。が、今回はここまでで留めおく。
|