 |
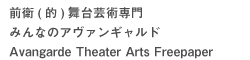 |

![]()
「夢うつつ」の世界と対峙するために――2023年演劇回顧
藤原央登(劇評家)
新型コロナ禍と演劇状況の推移
新型コロナウイルスが日本に流入してから4年目となった。2023年の5月には感染症法上の分類が季節性インフルエンザと同じ5類へと移行し、法律上は行政が各種の措置を講じて関与する必要がなくなった。新型コロナの正体が未知で、緊急事態宣言が発出されるほど感染者数が日々増加していた頃は、クラスター(集団) の発生を防ぐべく、3密(密閉・密集・密接)を避けることが全国的に求められた。その実際的な対策として、飲食店に営業の自粛が要請されたり、県境をまたぐ外出や旅行がはばかられた。だがそれは法律的根拠のない、政府や自治体からのお願いベースによる自粛であった。法律を根拠に都市封鎖を講じた欧米諸国とは異なる措置ゆえに、自粛や緊急事態宣言がいつ解除されるのかが不明確となった。そのため全ては世論やマスコミの動向次第という、空気による支配が醸成された。
新型コロナの5類移行からもうすぐ1年が経とうとする現在、そのような空気は嘘のように晴れている。新型コロナによる過剰な自粛とそのストレスが数年間続いたのだから、これを機にもう良い加減に解放されたい。新型コロナが5類に移行した途端に空気が変節したのは、このような国民の欲求がそうさせたのだろう。WHOが新型コロナの緊急事態宣言の終了を発表したのも2023年5月だが、脅威は消えていないと警告もしている。実際、5類への移行や緊急事態宣言を終了したからといって、新型コロナが消滅したわけではない。その代わりに国内でもインフルエンザが流行し、北京など中国北部では2023年10月半ば以降、子供を中心に「謎の肺炎」が流行したことに対して、新たなウイルスかと警戒感を抱く人もいた。にもかかわらず世界の大分は、コロナにかかずらわっていられないとばかりに、過去のものとして忘却しているのが現実であろう。科学的見地の面から何が正しいのかというコンセンサスがなく、大方針を立てて法律で規制することも人権などを理由に忌避した結果、規制することも緩めることも空気が支配した。これが日本の新型コロナ対策の全てだった。そのことは第二次世界大戦の戦争責任問題にも通じる、この国の無責任体質の姿を令和の時代でも繰り返しただけであった。
ロシア・ウクライナ戦争とイスラエル・ハマス戦争に続き、米中対立や台湾有事、北朝鮮問題を含めた東アジア情勢の混沌が予見されている。数年先にかけて世界はますます不透明になり緊張の高まることが危惧される中、再び空気によって世論が形成され、それが政治にプレッシャーをかける事態が起きかねない。先の戦争や新型コロナ対策のように、国民感情が政治行政の決断の一端を左右するシステムは、その結果の悲惨さを最終的に国民が背負うことになるという意味で、悲劇以外の何物でもない。
新型コロナ禍が上記のように推移する中、私が観た範囲では、出演者などの体調不良による公演の中止は、昨年で2件ほどあった。公演中止の理由が新型コロナが理由かは明らかでなかったが、ほぼコロナ前の公演状況に戻ったと言えるだろう。当然、客席を一つ飛ばしにしてソーシャルディスタンスを確保したり、仕切りを設置する対応もなくなった。コロナ禍初期にあった、俳優がマウスシールドを着用しての演技、最前列の観客にフェイスシールドの着用を求めることもない。俳優同士が飛沫を飛ばしながら近距離で会話するシーンでは、観ていてヒヤヒヤしたこともあったが、そんな気持ちももはや生じない。ライブ配信する公演は一部では継続されているが、YouTubeを用いた動画作品、VR演劇のような試行錯誤しての創作はなくなった。しかし改めて振り返れば、3密を伴ってこその演劇は、コロナ禍では最大の危機であったはずだ。だからこそ私は演劇という芸術形態は必然的に変革を余儀なくされるだろうと予想したし、無観客配信や動画配信はそのような動きの一環として捉えていた。そんな中で革新的だったのは、庭劇団ペニノを主宰するタニノクロウによる東京芸術祭2020・芸劇オータムセレクション『ダークマスター VR』(原作=狩撫麻礼、画=泉晴紀((株)エンターブレイン「オトナの漫画」所収)、脚色・演出=タニノクロウ、2020年10月、東京芸術劇場 シアターイースト)とタニノクロウ秘密クラブ『MARZO VR』(作・演出・監督=タニノクロウ、2020年12月、BUoY)の2つのVR演劇であった。VRゴーグルを着用しての仮想空間での観劇体験は、劇場に移動するアナログ性と感染対策を両立させた試みとして、今後の演劇への新たな展開として期待を抱かせられた。だがそのような動きは広がることなく、単発の試みに終わった。5類への以降によってすっかり立ち消えになり、そして以前のような濃密な演劇空間が戻ったという次第である。緊急事態宣言が発令され劇場が閉鎖になってからの様々な試行錯誤は、結局は平時に戻るための一時的な措置であり、異例の対応だったというわけだ。確かに金銭的なコストや手間をかけて普段とは異なる創作を試みることは、演劇人にとっては過大な負担であったろう。それだけでなく、感染リスクを避けるために稽古場でもマスク着用と手指消毒を徹底し、定期的な換気のためにこまめに休憩時間を確保するといった環境作りは、精神的なストレスも与えたはずだ。正直なところ観客としての私も、かつてのような観劇の醍醐味が戻ったことへの安堵を覚えもした。しかしこのような演劇の平時化もまた、新型コロナへの世間の空気が変容したことと平仄を合わせたものである。そのことは忘れてはならないだろう。そう考えた時、新型コロナ禍が終わったものと見なし、本当に忘却していいのだろうかという疑問が湧く。そのことはつまり、自然災害に典型的なように、平時が訪れるまでひたすらやり過ごし、その都度、ゼロにリセットすることを繰り返すだけで良いのかという問題である。新たなパンデミックはいつかまた来ると言われている。2024年元旦に発生した能登半島地震は、大地震はいつでもどこでも起き得るという意識を突きつけた。そしてウクライナや中東で起こっている戦争。混沌とした世界情勢の中で、新型コロナ禍が平時に移行しつつある今だからこそ、そのように問い直すことは重要である。以下、新型コロナ禍の日々を思い起こさせる舞台に言及することから始めて、そのことを平時の時間軸の中では見過ごされている事柄へと問題を敷衍させながら、2023年の演劇を回顧したい。
コロナ禍初期の記録劇
新型コロナの影響が日常生活に影響を及ぼし始めた、2020年3月からの数ヵ月間を我々はどのように感じ過ごしたか。そのことを今の時点から内省させた舞台が、劇作家女子会。feat.noo クレバス2020『 It's not a bad thing that people around the world fall into a crevasse.』(作=モスクワカヌ(劇作家女子会。)、演出=稲葉賀恵、2023年9月、シアター風姿花伝)である。劇中、新型コロナに感染した引きこもりの女性が登場する。彼女は夜、二階の窓から顔を覗かせ、人がいない街を見つめながら「世界が夢うつつ」だとつぶやく。この台詞ほど、あの頃の日々を的確に捉えた言葉はない。それを3年後に聞いた私は、紛れもない現実なのに異様だった日々の記憶が蘇ると共に、すでにそれが薄らぎつつあることを痛感させられた。
総勢17名の俳優が登場する群像劇は、コロナ禍をいかに過ごしたかを様々な若者にインタビューしたエピソードが基になっている。コロナ禍に関連するニュースや社会情勢を題材にしたものも含め、50本の短編作品を長編作品に構成したものが本作だ。各短編はあやとりのように他の作品と交代しながら、少しずつ進行する。そのため、同一世界と時間の中で、全てが同時並行で存在しているように感じさせる。ストールと包丁を手に公園の木で自殺しようとするが、青姦中のカップルと目が合ったという女性の一人語りから始まる、エピソード群の一端を挙げよう。不要不急の外出と県境を越えた移動の制限に悩む女性と、コンビニでの買い物を冒険と捉える男性。里帰り出産してから東京に戻れなくなった妻、コロナ感染者の苦痛、派遣の日雇いバイトがなくなり、ホームレスになった青年。東京の友人たちを頼って緊急事態宣言中に避難した、幼少時より実父からレイプされてきた女性。緊急事態宣言が出ている中、10月に予定している公演を実行すれば100万円の赤字が出るから公演を中止にするべきと進言する制作担当者と、この先の状況によっては客席を減らせば公演ができるかもしれないから、ギリギリまでその判断を待ちたいと悩む劇団主催者も登場する。そして客席を3方に設置した空間の背景の壁と上手と下手上方に設置されたモニターには、感染者数が日々増えてゆく様や緊急事態宣言の発出、アベノマスクの揶揄などをポストする高校生のX画面や、ステイホームで流行したYouTuber風の映像が適宜投影される。
©松本和幸
また登場人物の中には、新型コロナ禍前の密な生活から解放されたことで、かえって精神疾患が快方に向かった女性もいる。一方、地球温暖化を含めた人間にとっての危機は、地球の側からすれば人類への大きな警告である。一連の事象は地球の自己免疫反応であり、人類を死滅させようとする動きのひとつとして、コロナ禍があると主張する入院患者もいる。劇場が閉鎖になって演劇公演の中止に追い込まれたアーティストへの支援として、東京都による「アートにエールを!東京プロジェクト」という支援事業があった。アーティストやスタッフが動画作品を創り、出演料としてアーティスト一人あたり10万円、作品全体に上限100万円を支給する事業だった。劇中には、バンドを組んだ登場人物たちの作った動画が流れる。コロナ禍によって、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」が危うくなり、生き辛さが増している。そのことを訴える歌詞を叫びながら歌ってダンスする人々と、インパクトのあるフォントで「健康で文化的な最低限度の生活」の文言を無数に挿入したヴィヴィッドな映像である。移動の自由や創作活動を制限されるばかりか、演劇人のアルバイト先としても選ばれている飲食、宿泊サービス業を中心に営業が自粛されたことで、多数の人々が職を失ったことであろう。生活基盤と将来の見通しが立たなくなる中でも、感染対策で3密を避けるニューノーマル=新しい生活様式が求められる理不尽さ。激変する社会生活で最も煽りを食ったのは、例えば本作に出演する俳優に代表される若者たちであろう。奇異な毎日の中でも、健康で文化的な新しい生活を余儀なくされた若者たちの悲喜こもごも。それが社会への当てこすりのような映像や時に自虐的な笑いをまぶしながら、2時間35分の中でほぼ網羅されている。俳優が客席通路に分け入りながら演じることで、誰の身にも等しく降りかかった新型コロナ禍の危機を、改めて観客とフラットに共有する空間が出来した。
天井からは数多くの電球が吊り下げられている。夜空の星に見立てられたそれらを、俳優たちが見つめて幕となる。電球の中にはワンポインの小物も混ざっており、俳優たちは各々、それらを手に取って役柄を演じる。光が人間を包み込む演出からは、コロナ禍初期からの3年間を生きた、観客を含むあらゆる者たちを称揚する温かな印象を受けた。一方で、地球に届く星の光は、実際にはすでに消滅した過去の惑星の光である。電球に混ざって吊り上げられた小物群も星だと捉えれば、コロナ関連で亡くなった人々を弔う光にも感じた。
本作が優れているのは、「世界が夢うつつ」だった過去を、現在からセンチメンタルに振り返るだけではない点にある。ステイホームで髪をレインボーカラーに染めた女性が生き方を見つめ直し、そのままの髪色で働ける仕事を探す場面がある。いろんな事柄をポストする高校生も、皆が同じような生活を送っていた緊急事態宣言前の密な日々こそ、人間にとってはストレスを与える毒であることに気付いたと述べる。そして自分は自分だけの新しい生活を模索したいと作文に綴る。各人がコロナ禍から糧を得ることで、遠い昔にも感じられる3年前が、確かな現実だったという実感を持つことができる。あの日々を特異な「夢うつつ」として空白にするのではなく、それを確かに通過して現在を生きているという、地に足が付いた教訓をいかに持てるか。その態度を持つことは、いつかまた来る事態への備えと対処をする上でも重要なのだ。そのことを改めて今に伝える、貴重なコロナ禍初期の記録劇であった。
北朝鮮拉致事件・政治テロといった過激思想を抉る
「夢うつつ」という形容が相応しい舞台は、北朝鮮の拉致問題をテーマに据えたNODA・MAP『兎、波を走る』 (作・演出=野田秀樹、2023年6月~7月、東京芸術劇場 プレイハウスほか)にも通底している。1977年11月、横田めぐみさん(当時13歳)は下校中に、新潟県の自宅近くで北朝鮮の工作員に拉致された。まさにあの日から異国の地での生活を強いられているめぐみさん。そしてある日突然、娘を拉致されたまま、現在においても生きざるを得ない母・早紀江さん。早紀江さんは、拉致被害者家族連絡会での活動を通して北朝鮮の非道を国内外で訴えて、めぐみさんの奪還と帰国を信じている。彼女たちの日々は、嘘のような信じられなさという意味で、まさに「夢うつつ」である。そこにはもちろん、家族会元会長のめぐみさんの父・滋さん(2020年死去)、現在の家族会会長でめぐみさんの弟・拓也さんとその双子の弟・哲也さん、そして2002年10月以降に帰国した拉致被害者とその家族、めぐみさんの他にも今なお、「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」(警察庁HP)として全国の警察が把握している「特定失踪者」たちが、同じような境遇に晒されていた/いることも意識しなければならない。だが、当事者たちが国内外で様々な救出活動を政府やメディアを通じて訴えているにもかかわらず、日本政府と国民世論はあまりにも微温的である。当事者家族と国民との間で埋まらないズレがなぜ生じるのか。それは現在形の問題としてあの日から地続きに生きる家族たち当事者と、事件をある種の歴史的事件として受け止めて過去と現在とが切断している大多数の非当事者たちとの間で、身体の内的な時間軸の捉え方が齟齬を来しているからだ。拉致問題の当事者たちにとって国民世論の停滞は、家族が離散したことに輪をかけて、彼らをさらに過酷な状況に追いやっている。拉致問題の当事者たちの過酷な人生を簡単に推し量ることはできないし、安易な同情を寄せるべきではないのかもしれない。とはいえ北朝鮮による拉致は、独裁国家によって日本の国家主権と国民の生命と安全が侵害され続けている事案だ。本来は非当事者だとしてもそのことに対して怒り、それこそ日本政府を突き動かす空気を醸成しなければならないはずだ。本作の物語自体は虚構を強める舞台表象と相まって、問題がいつまでも解決しない堂々巡り感を強く抱かせる悲劇である。円環的で出口のない物語だからこそ、異国の地から帰国を求める女性のこだまが響く幕切れに、日本政府と国民は拉致問題へ関心を持ち続け、忘却してはならないというメッセージを私はしっかりと感得した。
時に古今東西の文学を換骨奪胎しながら言葉遊びを駆使して、連想が膨らむ野田秀樹の劇世界。自由奔放な物語を走り続けた登場人物たちは、いつしか近現代史で起きた事件や事故の当事者であることが明らかとなる。『ふしぎの国のアリス』『ピーターパン』、チェーホフ、ブレヒト、シェイクスピアと、本作でも様々な文学や作家が散りばめられている。チェーホフ『桜の園』に登場する没落貴族・ラネーフスカヤならぬ元女優ヤネフスマヤ(秋山菜津子)の所有する劇場が、競売にかけられる。買い手は新興階級・ロパーヒンに比せられた不動産業者シャイロック・ホームズ(大鶴佐助)であり、彼はその地を統合型リゾートの開発に充てる。件の劇場にはネバーランドに通じる穴が空いている。その穴倉は親に捨てられた迷子たちが住む特殊機関であり、東急半ズボン教官(山崎一)らによって彼らは工作員教育を受けている。出かけたきり失踪してしまったアリス(多部未華子)も、前世が永遠の子どもを志向するピーターパンだったという、脱兎(高橋一生)に導かれてこのネバーランドに迷い込む。本作は、見かければすぐに見えなくなってしまう脱兎を追いかけて穴倉に落ち込んだアリスの母(松たか子)が、アリスを捜索する物語である。彼女は暗号を解くことで、穴倉が工作員の教育場であり、脱兎は優秀な工作員であること、そしてアリスは工作員に拉致されたという失踪の真実を知る。失踪したアリスが横田めぐみさんであり、アリスの母は早紀江さんが重ねられている。そして脱兎はスパイ教育を受けた工作員であり、1993年に韓国に潜入した後に同国へ亡命した安明進がモデルである。めぐみさんを拉致したのは安明進ではないが、その4年後に、北朝鮮で横田めぐみさんら日本人拉致被害者を見たと証言したことで、拉致問題が確定的に報道されるきっかけとなった。そして彼は2016年に中国で消息を絶つ。舞台の終わり近くに拉致のシーンが再現される。白の防護服を着た工作員たちが話す様子を海岸で目撃したアリスが、彼らにクロロホルムを嗅がされて意識を失う。そのまま手際良く袋に詰められたアリスは、船舶の底に収納される。一連のシーンが『新世界』をBGMに、流れるようにスローモーションで展開される。脱兎は、見つかると姿を消してしまうとアリスの母に語る。だが実際は彼が工作員故に、見た者が消されてしまうので決して見てはいけないということだったのだ。そんな脱兎が優秀な工作員になったのは、穴倉から早く脱出するためである。アリスの母と心を通わせた彼は、アリスを取り戻すべくネバーランドの境界線を再び渡るものの、失敗して消息を絶ってしまう。そしてアリスの母は、こだまのように響くアリスの心臓の鼓動をいつまでも感じながら、再び抱き合えることを願って、ここにはいないアリスを抱きしめて終わる。アリスとアリスの母がしっかりと抱き合う中、ブレヒト幕が彼女たちの前を横切るとアリスが消えて母だけが残される。多様されるブレヒト幕の演出が、悲痛さを強調して印象的であった。
劇中、アリスの母も北朝鮮の工作員教育を施されて、アリスが辿ったのと同じ境遇を受ける。またブレヒト『コーカサスの白墨の輪』(1944年)には、一人の子どもを巡って、二人の女性が争う裁判のシーンがある。子どもの左右の手を両側から引っ張るが、子の痛がる様子を不憫に思い、先に手を離した方を真の母だと認定する有名な場面だ。これを引用した場面では、人形の子どもの両手を、アリスの母とアリスが引っ張り合う。この子どもはアリスの母がアリスを探して迷子案内所を訪れた際に、案内員から押し付けられた子である。しかし当のアリスもまた、その子どもを産んだ迷子の母だと主張するのだ。母が子を求める一方で、娘もまたその子を母として求める様は、アリスを追う母を追う母……という終わりなき円環を連想させる。拉致問題が解決せぬまま時間だけが流れ、被害者の帰国を求める者が次世代に引き継がれている現在の状況を、このシーンとアリス・アリスの母という連結的な役名に集約されている。
『ふしぎの国のアリス』の世界を体現する、虚構の視覚化が圧巻だ。背景の黒い壁がひし型に左右に開くと、一面の合わせ鏡が出現。白兎たちの乱舞や巨大な懐中時計の振り子が虚焦点に向かって何重にも映り、めくるめく幻想世界が出来する。また劇場が建て替えられる統合型リゾートは、VR世界が体験できる施設であるため、現実世界も虚構化してゆく。アバターと同化した人間は、AIが支配する仮想空間に惑溺し、ヤネフスマヤ、チェーホフに擬せられた第一の作者?(大倉孝二)とブレヒトに擬せられた第二の作者?(野田秀樹)の3人も、ネバーランドへと落ち込む。それまでに現実世界で進行してた物語は、かつてヤネフスマヤが母親と観た『アリスの話』を最後に上演すべく、第一の作者?と第二の作者?が戯曲の執筆を競い合うというものであった。戯曲が書き換えられると、本作の物語展開もそれに合わせて進行するという、劇中劇の構造になっている。そんな彼らにVRゴーグルを着用させてネバーランドへと誘い込むのは、東急半ズボン教官こと第三の作家?・初音アイ(AI)である。東急半ズボン教官の言葉がマイクを通ると音声変換され、プロジェクターに投影された初音アイの言葉として空間に不気味に響く。つまり穴倉で行われている秘密の工作員教育は、VRに代表されるヴァーチャル世界によって指示されていることが判明するのだ。ネバーランド=北朝鮮で進行する夢のような出来事は、異国の地やアンダーグラウンドの世界に限定されるのではない。もはや我々が生きる地上の現実世界もAIとVRに支配され、人間は仮想世界に夢心地になっている。アリスとアリスの母の関係性と同じく、穴倉(内)と地上(外)が一対で虚構をなして円環しているということ。世界全体の虚構化が描かれるのだ。先に記した合わせ鏡だけでなく、ブルーライトで縁取られる舞台美術や、ブレヒト幕に投影される俳優の映像が3次元に見えるプロジェクションマッピングといった舞台表象を駆使して、野田作品としてこれまで以上に虚構度の高い舞台を設えていた。
全世界の虚構化は近年のことだけではなく、実はいつの世も容易に市井の人間を蝕んできたのではないか。そのことを、かつての新左翼運動と重ねている点も重要だ。劇場の取り壊しに人々が座り込みで反対する展開に、農民たちの中にヘルメット姿の新左翼の活動家たちが混ざった、三里塚闘争(成田闘争、1966年~)の記録映像が投影される。その後、座り込みをしていた若者の活動家の一部が、舞台後景で手を振りながら階段を上るシーンが描かれる。この光景は、運動に行き詰った若者が、地上の楽園を求めて起こしたよど号ハイジャック事件(1970年)を意識したものだろう。よど号ハイジャック事件は、赤軍派内のグループの一つが起こしたものである。彼らは世界同時革命を達成するため、日本に敵対する北朝鮮に国際根拠地を置こうとして事件を実行した。後に赤軍派は京浜安保共闘革命左派と合流して連合赤軍を結成し、群馬県に築いたアジト(山岳ベース)でリンチ殺人を含む凄惨な内ゲバを起こし、その残党が長野県であさま山荘事件を引き起こす(1972年)。虚構世界は、AIやVRといったバーチャル機器に身体が操作されることだけではない。過激思想に走り暴力で世界を変えようと夢を抱くことも、極端な思考で認識が侵されているという意味では同様だ。かつては人的ネットワークなどでそのような思想が一部のサークル内で濃く共有されていた。だが現在はネットやSNSによって距離の懸隔なく、飛び交う差別的言説やフェイクニュースに煽られ、広く過激思想に浸りやすくなっている。それによって、過激思想を持つ者が一部の集団としてある種見えやすい形で存在しているのではなく、細かなフラグメント(断層)があちこちに刻まれるように、社会の中に鬱々とした少数派が孤立しているのが現在の状況である。その中の断層の一つが地殻変動を起こした事件が、安倍晋三元首相の暗殺(2022年)であり、現職の岸田文雄総理(2023年)の暗殺未遂という格好で表面化したテロリズムである。今や過激思想に突き動かされる政治テロは、「ローン・ウルフ」型としてたった一人でも行われているのだ。
本作のパンフレットで野田は、自身の世代の総括としてよど号ハイジャック事件のエピソードを挿入したと語っている。事件を引き起こした犯人たちは、拉致問題にも関わった疑いが持たれている。もしそうであるならば日本人自身が拉致を引き起こし、当事者と家族を今も悲しみの迷宮に押し込んだ責任の一端を担ったことになる。そのことへの自責を含めた想いが、北朝鮮の拉致問題と正面から向き合う作品を創らせたと私は受け取った。これは演劇人が左派リベラルにシンパシーを覚える中では、極めて珍しいことだ。身勝手な妄想を抱いてネバーランドを構築しようとする者と、ある日突然、日常が奪われて夢の世界に堕ちたその被害者家族。夢を巡って正反対の境遇に置かれた人間の姿は、内と外が虚構のマンダラを描いて円環する世界を表出させる。そんな十重二十重に構築された虚構世界は、終盤に向かって謎が次々に判明することで華やかなフィクションの覆いがはぎ取れ、松たか子ら俳優が一個の人間として顕わになる。観客は裸形となった俳優の人間性に触れることで、日本人が決して忘れてはならない北朝鮮による拉致事件へ思いを馳せるよう、覚醒させられたのである。
戦争の理不尽さを寓話的に示す、別役劇における「象」
当事者にとってはもちろんのこと、全世界の人々にとって「夢うつつ」のような現実の出来事となっている喫緊の事象は、2つの戦争である。一つは2022年2月24日、ロシアが「特別軍事作戦」と称して首都キーウなどのウクライナ各地を攻撃して戦端が開かれたウクライナ戦争。二つ目は2023年10月7日、パレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスが、イスラエルに大規模なロケット攻撃と戦闘員によるテロ攻撃を仕掛けたことで始まった、イスラエルとハマスとの戦争である。戦地の広がりによって、すでに第三次世界大戦が始まっていると見る向きもある。そのような不安をもたらす戦争は、最終的にはいつも弱い立場の存在を翻弄する。そのような事態を寓話的に描くアクチュアルな作品が、日本劇団協議会『森から来たカーニバル』(作=別役実、脚色・演出・振付=スズキ拓朗、下北沢 ザ・スズナリ、2023年11月)だ。1994年に演劇集団 円が初演した別役実の戯曲を、スズキ拓朗の持ち味であるコミカルなダンスを取り入れた、スピード感のある音楽劇仕立てで描いた。そのため別役劇に特徴的な、日常会話のズレを丹念に積み重ねることで常識を問い、世界の不条理がじんわりと浮き出てくるような見せ方ではない。ショーアップする音楽と照明でテンポを作って狂騒性を高め、特徴的な象をかたどった背景の舞台美術とそこに投影される映像が、絵本の世界のような柔らかな印象も与える。今日の戦争の時代を、寓話性を際立たせる舞台表象によって暗喩的に示すのだ。だがそこから、観客が能動的に作品を読み取ろうとすることで、かえって身体の五感でダイレクトに世界的な紛争を体感させられる作品となった。そう思えば、別役劇には『スパイ物語 へのへのもへじの謎』(1970年)、『雨が空から降れば』(1997年)を始めとする音楽劇がある。小室等が率いるフォークグループ・六文銭が『スパイものがたり』の劇中歌として提供した『雨が空から降れば』は、ヒット曲にもなった。それを踏まえて本作の演出を別役実の音楽劇のラインにあると捉えれば、真っ当な方法だとも言えよう。音楽劇として書かれてはいない他の別役劇も、同様の演出で試せるのではないかと思わせるものがあった。
どこかわからない場所に妻(山﨑薫)、編み物をする女(よし乃)、乳母車の女(橋口佳奈)、近所の奥さん(竹本優希)、ウェートレス(山下直哉)と、赤ずきんを思わせる赤と白の衣装が印象的な5人の女がやってくる。彼女たちはそれぞれ、夫を亡くした未亡人のようだ。そこへ二人の担架の男(鳥越勇作・鈴木幸二)が次々と死体を運び込む中、妻は亡き夫との思い出の日々を回想する。そんな状況の中、天気予報を思わせる映像が投影される。台風に見立てられたカーニバルの男(石渕聡)の顔が、こちらにやってくるというコミカルな映像だ。本作には森(諏訪創)が登場する。迷彩服を着用して顔を黒く塗った彼が、ブーブー笛のような音を奏でる楽器を吹く。すると騒然とした音響とストロボのような照明と共に、カーニバルの襲来が告げられる。そして後述するように、戦争の脅威の象徴となった象の舞台美術が、背景から迫ってくるのだ。カーニバルの男の率いる象が、女たちと土地への差し迫った危機として暗示される。カーニバルの一軍がもたらす喧騒に、それとは正反対の戦争の悲惨さが重ね合わされているのだ。と同時に、街の工場から青酸カリが盗難に遭ったというニュースも流れて脅威が増す。
夫の死はどうやら、カーニバルの男の指示で象が盛った、青酸カリ入りのパフェを食べたことによる毒殺によるものらしい。しかし夫自身が自ら毒殺されたように仕向けて、象に責任が向かわないようにしたと、カーニバルの男は語る。ここには、戦時下の人道問題や戦争責任の曖昧さの暗喩が孕んでいる。そんな象は、四角い穴をいくつか空けた、白い壁で表現される。象の足を表現するために開けられた穴には黒いカーテンが付けられているため、舞台後景から前に迫ると、舞台に対して縦に横たわる夫や小道具を飲み込む格好になる。そのために、人や物を圧殺しながら迫る舞台美術の象が、漠とした戦争の圧力や恐ろしさの象徴に見えてくる。ところで別役実の初期作品には、『象』(1962年)がある。原爆で負った背中のケロイドを町中で見せびらかして自尊心を保つ病人。そして被爆者の存在はすでに忘却されており、あとはひっそり我慢して生きていくしかないと、彼を引き留める甥。対立する二人の姿から、被爆者が置かれた立場と、先の戦争に対する戦後の人々の意識を滲ませる傑作である。タイトルにある「象」はこの作品では登場しないし言及もされない。しかし今回の『森から来たカーニバル』を踏まえると、象が戦争に類する獏たる脅威であること。しかもその脅威すら誰かやどこかからの大きな力によって、受動的に操られて暴走するという意味での制御不能のものであることが了解できた。
舞台ラストではこの壁が、舞台後景で前に倒される。すると舞台美術の裏側らしいゴツゴツとした木枠が露わになる。その光景は、戦争によって街の建物などが倒壊し、廃墟になった雰囲気を思わせる。そしてゴツゴツとした美術の裏側を椅子とテーブルに見立て、腰を掛けた夫妻がお茶を飲むシーンがラストに訪れる。だが穏やかな会話の最中に、夫が舞台全面によろけながら歩いて倒れる。つまり廃墟となった街で、妻が穏やかだった日々を寂しく回想する物語だったのだ。
ここには『兎、波を走る』でアリスの母が、アリスがいるかのように抱きしめたり、ネバーランドからこだまする声をしっかりと聞きながら娘の帰りを待つ母の姿と重なる。2つの作品の女性の姿に共通するのは、戦争や国家犯罪による被害者が女性や子供といった弱者であるということである。本作に登場する女性キャラクターが、似た服装をしているために妻が5人に見えることや、言葉を発することなく舞台上を跳ね回るお嬢さん(小林らら)が夫妻の子供に見える点に、そのことが集約されている。この辺りは、ギリシャ悲劇『トロイアの女』にも重なる。エウリピデスによる『トロイアの女』は、古代ギリシャのミケーネやスパルタなどによるギリシャ王国連合とトロイア王国との間で起こった、戦争が生んだ悲劇を描く。敗れたトロイア側の女性たちが多数、ギリシャ軍の捕虜となり奴隷として扱われた。その中には王妃ヘカベもいた。へカベの娘や息子の妻、その子供が連行される。そしてギリシャ軍が放った炎でトロイアが燃え尽きる。ギリシャ悲劇から現在に至るまで、止まぬ戦争の被害者が市井の人々であることは、イスラエル軍に攻撃されたガザ北部の病院で多数の子供たちが殺害されたことからも明らかだ。ハマスの戦闘員を標的にするため、一般住民は南部へと避難するようにイスラエル側は促していた。だがイスラエルはその南部にハマスの主要な拠点があるとして、空爆と地上からの砲撃を実施しており、国際社会からはジェノサイド(民族浄化)だとの非難が高まっている。そういう情勢の中で上演された本作は、別役劇の不条理を、まさに戦争という究極の不条理へと思いを至らせる、時宜にかなった作品だった。
運命の有無をどう捉えるか
新型コロナ禍、北朝鮮による拉致問題、全領域の仮想空間化、ウクライナ戦争、イスラエルとハマス戦争といくつかキーワードを示しながら2023年の演劇を振り返ってきた。これらを集約する言葉はやはり、虚飾にまみれた「夢うつつ」の世界に我々は生きているということになるだろう。全世代的に忘却しつつある拉致問題への覚醒をもたらした『兎、波を走る』のように、全世界的に嘘のような事態に見舞われる中、夢から醒めることは可能なのか。それは換言すれば、生じる事態にただ振り回されるのではなく、そこに主体的に関与する余地はあるのかという問題へと至る。イキウメを主宰する前川知大が紡ぐ作品には、常にその眼差しが含まれている。世田谷パブリックシアター『無駄な抵抗』(作・演出=前川知大、世田谷パブリックシアター、2023年11月)にも、そのことを考えさせられた。『森から来たカーニバル』は『トロイアの女』を連想させたが、本作はギリシャ悲劇のソフォクレス『オイディプス王』を下敷きにして創られている。テーバイの王オイディプスは、国に災厄をもたらしている原因が先王を殺害した犯人にあることを突き止める。だが先王である実の父を殺した犯人がオイディプス王自身であり、さらに実母と知らずに迎えた妻と姦通してしまう。それら一切を、オイディプス王はあらかじめ預言者によって告げられていた。オイディプス王は予言が当たっていないことを証明しようとするが、結局はその信託通りに行動していたことを知る。そして彼は最後に、自らの運命を呪って両目を突き、王の座を降りて放浪の旅に出る。本作はこのギリシャ悲劇から、運命や人生をいかに引き受けるかを抽出する。
山鳥芽衣(池谷のぶえ)は、小学校時代の同級生で、今はカウンセラーをしているがテレビにも出ていた有名な元占い師・二階堂桜(松雪泰子)から小学校の頃、「人を殺す」と予言される。それを実現せぬよう、芽衣は子供の頃から慎重に生きてきた。医療事故が少ない歯科医になり、痴情のもつれを回避するべく恋人を作ったりもしなかった。そんな芽衣の呪縛の解明が物語の主軸である。芽衣の母は、父親の兄の叔父・山鳥五郎と不倫していた。そして芽衣の実父は五郎であり、彼は一家を金銭的に支援しつつ、中学生の頃、芽衣を妊娠させてもいた。五郎に引け目を感じていた父は、全て知っていたにもかかわらず、母と兄に暴力を働いた末に蒸発。そんな状況の中でも、妊娠した芽衣は預言を守るために中絶することができず、子供を児童養護施設孤に預ける。そしてホストの鈴木理人(渡邊圭祐)が養護施設で育った自身の子供とは知らず、芽衣は貢いでいる。一方で死期が迫った五郎は、近親相姦的な関係になった芽衣と理人を別れさせるべく、探偵・佐久間一郎(安井順平)を雇って常時監視を続けている。佐久間は、五郎の孫・山鳥文(穂志もえか)をメッセンジャーに、手紙を通して連絡を取り合っている。理人と同じ養護施設で育った色川りさ(清水葉月)も、自身の子供を施設に預けており、金銭的に困窮している。また養護施設の元職員で、今は駅ビルの警備員をする日暮栄(森下創)や、芽衣の兄・山鳥潤(森隆二)が登場する。誰かが誰かと関係し合い、全員がゆるやかに繋がる登場人物たちが集う中で、先に記した真相が判明する。
舞台は半年間、電車が止まらず通過するだけになった街の、すり鉢状になった駅前広場である。他の登場人物たちはベンチに腰掛けたりして、他人の話に耳をそばだてて聞きながら、広場に溶け込むように佇む。すり鉢状の空間は、古代にギリシャ悲劇が上演されスポーツも催された野外劇場を意識したものだろう。直接民主制が採られた古代ギリシャの野外劇場は、国民が直接政治に参加し討論する場でもあった。野外劇場は政治経済や文化の拠点であり、「人の集まる所」という意味で「アゴラ」と呼ばれた。登場人物たちはすなわち、駅前広場という名の「アゴラ」に集い、繙かれる芽衣の運命に立ち会うコロス(古代ギリシャ劇に登場する合唱隊)の役割も果たすのである。そういう意味で階段状になったすり鉢状のセットは、我々が座る客席と対を成している。つまり劇場空間全体で、舞台を円形に囲う格好に設えられているのである。本作には固まったまま動かないスタチュー(彫像の芸)でもなく、ただ無言で座ったまま何もしない大道芸人・ダン(浜田信也)が登場する。舞台を移動しながら物語の成り行きを淡々と見つめるダンの存在は、観客の代表であると共に、劇のラストでは運命を司る神のような役割も果たす、ピエロでありかつトリックスターでもある人物だ。
芽衣は最後には、地元の名士として知られる山鳥一家を破綻させることになろうとも、小学校の校長を歴任し教育委員会の教育長まで務めた五郎からの性被害を告発することを決意する。それによって結局は、父殺しを行ったオイディプス王と同様に、人殺しの預言を成就させてしまう。ちょうどその頃、駅に電車が止まらないために集客が減少し経営が悪化したカフェ店長・島忠(大窪人衛)が、ポイントを切り替えて電車を脱線させる。そしてその次にやって来た電車と激突する。その衝撃音が、決意する芽衣の姿に重なり、BGMのような効果を与える。過去を含めた現状を変えるためには、自らが選択し行動しなければならない。芽衣の覚悟の強さが、電車を脱線させるという犯罪行為に接続されて倍化する。もしかすると芽衣の行動も含めて、あらかじめ運命付けられていたことなのかもしれない。しかし人間は運命に動かされているに過ぎないとは、誰も説明できないし証明のしようがない。そもそも運命などないのかもしれないのならば、やるだけのことをやって、それによって引き起こされる事態は自らの責任として受け入れる。そのような疑似主体的な態度でいる方が、人間にとって幸福なのではないか。未来がどうなるか分からず、ifの人生がない不安が充満している世界を生き抜くための人間の構えのようなものが、芽衣の覚悟とそこに重なる電車の衝撃音のシーンに、突き詰めた形で顕れている。
先行きが不透明な未来へと自ら一歩を踏み出した芽衣に対して、りさには救いが訪れる。借金を抱えていたりさは、ホストで稼いだ理人から150万円が入った封筒を差し出され、「あげる」と言われる。だがりさは、ほどこしを受けて自分が惨めになることが嫌でその受け取りを拒否。そして椅子に座ったダンが膝の上に置いたハットに現金を入れ、その金額に相応する芸をするよう求める。しかしダンはその金を何もしないことの対価として受け取ってしまう。そのことに反発したりさが金を取り戻そうとダンを追いかけるが、その内に誰かが受け取り、そしていつしか登場人物たちの間で封筒がパスされてゆく。再び理人の手に戻った封筒をダンが手にし、スッとりさのポケットに入れる。ホストという職業は、市井の民が生んだ金を、身の丈以上に受け取ってしまう。そんな回り回って手に入れたあぶく銭を、せめて大切な人を助けるために再び回したい。そんな理人の想いは、こうして実現される。酷い境遇だったり不満を抱く人生だったとして、そこから能動的に行動するもあがくも、その者の自由だ。その結果として、人によっては悲惨なまま人生を終えることもあるかもしれない。何もする気が起きない虚脱感に苛まれることもあるかもしれない。しかし、回り回ってりさのポケットに現金が入るように、またとない幸運を手にすることもあるかもしれない。このシーンは、判別不可能な運命に翻弄されて不安に生きる我々を癒す。だからこそ、ダンが放つ「そういうものです」という台詞が、諦めではなく人間を救う温かな言葉として響いた。バイプレイヤーとしてコミカルなキャラクターで知られる池谷の、自然体の演技も魅力的だった。
先行きが不透明な世界を不安を抱いて生きていると、極端な意見や分かりやすい解決方法を掲げる人々や勢力にすがりたくなる気持ちが誘発する。それが、新型コロナ禍で生じた空気に流される世論や、ネットやSNSで企業や人々を一斉に攻撃して吊るし上げる炎上で溜飲を下げる現象の一因だろう。そのような空気の蔓延が、政治テロが発生する土壌にもなるのだ。それに自分が巻き込まれることを承知しつつ、己を失くさないためにやるべきことを見定めて、ただ淡々と実行してゆくこと。『 It's not a bad thing that people around the world fall into a crevasse.』に登場する高校生や髪がレインボーカラーの女性、そして芽衣のように、辛くとも身になると信じた何事かを芯を持って実行することで、周りの空気に翻弄されることから少しは逃れることができるのではないか。たとえその行動が間違っていたり失敗したとしても、自分で責任が取れる範囲内のものである限りは、やり直しが利く。そういう態度が、パンデミック後も次々と危機がやって来る世界で、疑似的にも主体的に考え行動して対峙するためには必要な方法である。そのことがひいては、戦争だけは避けようという絶対に譲れない防衛線を、たとえ世間や政府が悪い方向へと仕向けようとしても、惑わされずに堅持することにもつながるのだ。
INDEXに戻る
