 |
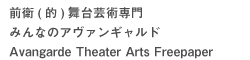 |

![]()
コロナ禍を批評する演劇的想像力
藤原央登(劇評家)
城山羊の会『ワクチンの夜』
2021年12月3日(金)〜12日(日) 会場 三鷹市芸術文化センター 星のホール
新型コロナウイルスのワクチンの有効性や、死亡事例との因果関係はあるのか。専門家も断定できないまま、大事なことが進行している。そのような状況を投影した喜劇だ。
ワクチンの効果を「嘘」に、副反応を「性欲」に置き換えて、性を原動力にしたすれ違いと暴力が展開される。この光景が例えば、「コロナ脳」と呼ばれたような、過剰に感染を恐れるあまりに差別的に他者を排除する、この2年間の異常な社会を痛烈に批評するのである。
2回目のワクチン接種を終えた夫妻。発熱してリビングのソファーに横たわった妻(岩本えり)を、色欲ジジイの義父(岡部たかし)が抱きついたり股間を触るなどのセクハラ行為をはたらく。アンニュイな佇まいの妻も、半ば確信犯的に男をその気にさせるような雰囲気がある。そんな妻は、ワクチン接種を担当した医師が、昔付き合っていた彼氏に似てるということで、息子・秋彦(朝比奈竜生)の大学の後輩・マスブチ(中山求一郎)を相手に、ワクチン摂取を再現する。そうする内に気分が盛り上がって、妻はマスブチとキスをしてしまう。発熱はワクチンによるものではなく、昔の男を思い出して湧き上がった性欲によるものだったのだ。
一方で義父は、マスブチの彼女・佐々木エリカ(春原愛良)を口説くべく、少しでも自分を若く見せようとする。自分が家の主人であり、息子である夫(岩谷健司)は隣にある森の番人だと嘘をつくのだ。エリカは義父から別の部屋で迫られることになるが、彼女がリビングに逃げ出してきた時に、妻とマスブチの情事を目撃してしまう。エリカはその腹いせか、引き込もり気質の秋彦に対し、映画などいろんな誘いをしてくれているがもう止めてほしいと、ストーカー扱いしてきっぱりと関係を絶って去る。
スナックのママと不倫している夫は、そのことを義父に責められた末に、互いに大ケガするほど殴り合う。それが元で、義父は持病の不整脈の発作を起こす。日が落ちて暗くなったリビングに、義父の遺体、顔面を負傷した夫、脱力してソファーに座る妻がいる中、フラれて号泣する息子が戻ってくる。誰も幸せにならない地獄の光景だ。
義父の嘘によって家族同士とマスブチとエリカたちとの間の会話がかみ合わなくなる。そのためにマスブチたちは、夫が家族内でどういう存在なのかが混乱する。またエリカのレポート作成のために、リビングテーブルで秋彦とマスブチを交えて検討している傍で、夫と義父の大乱闘が蹴り広げられる。こういった不自然な状況にマスブチとエリカは巻き込まれるが、割と普通に受け入れたり、むしろ会話の辻褄を合わせに行こうとする。そのおかしさが本作に、独特のテンポと文体を伴った、シュールな世界を出来させる。
加えて舞台の初めの方で、空腹のまま解熱剤を飲んでしまった妻に対し、胃に負担をかけないために、すぐに胃薬を飲むか食物を摂るかを巡って、夫・秋彦・義父が話し合うシーンがある。どちらが正しいのか彼らは自己主張を通そうとするが、そうこうしている内にも、どんどん薬が溶けていってるから!と、母親を心配して秋彦が訴える。
このように物語の端々に、何が正しいのかについての下地があるのだが、ワクチンと新型コロナを巡って、真偽不明の情報を元に事態が推移してきたこの2年間も、このシュールさと重なる部分が大きかったのではないかと思えてくる。
作品を彩るエッセンスとしては、2階でセックスする夫妻の喘ぎ声を気まずい雰囲気で聞く秋彦たちの姿。その後に夫が素っ裸で階下に降りてきては、エリカたちがいることを初めて知って、慌てて股間を押さえて戻ってゆくシーン(森の番人の伏線回収か?)など、妻が発する性の匂いと爆発力のある笑いが効いていた。
そもそも舞台は、観劇注意と共にナレーションをする劇場職員の口上から始まる。これから舞台上で起こる珍奇な出来事を、客観視することを冒頭で枠付けているのだ。コロナ禍が3年目に入って、ようやく事態を冷静に眺める演劇的想像力が生まれた。そのことに、私は胸がすく思いがした。
INDEXに戻る
![]()
突きつけられる、2018年~2021年の社会変容
藤原央登(劇評家)
ダンスがみたい!23 「新人シリーズ」受賞者の現在地2
水中めがね∞『有効射程距離圏外・Ⅲ』
2021年8月18日(水) 会場 d−倉庫
中川綾音が率いる水中めがね∞の作品からは、社会で生きることの鬱屈感や抵抗の意志を感じさせられる。時に暴力性を伴うことで、観る者にひりついた感覚を与える。一方でストリート系のカッコ良さやテキトーさもあるため、フッと肩の力が楽になる瞬間もある。攻撃的でストイックな中に、スマートさと脱力性が顔を覗くのである。それはカーテンコールで中川が見せる、キュートな笑顔と根の謙虚さを思わせる人柄によるものなのかもしれない。彼女自身に、この振り幅があるのだろう。
d-倉庫では、神楽坂にあった劇場・die pratze(2012年閉館)時代より、「ダンスがみたい! 新人シリーズ」(2004年~)を開催している。これは新人のダンサーやカンパニーのダンスコンペティションで、毎年、新人賞とオーディエンス賞が選出されてきた。2014年以来の「受賞者の現在地」と題された企画では、これまで各賞を受賞した個人と団体の現在の活動に改めて触れることができる。2回目の今回は、2015年以降の受賞者8組が出演した。私は4作品(杉田亜紀『うめぼしソロソロ』、茎『Love is swimming』、大塚郁実『ピーターと狼』、水中めがね∞『有効射程距離圏外・Ⅲ』)を観たが、最も印象深かったのが、水中めがね∞『有効射程距離圏外・Ⅲ』(演出・構成・振付=中川絢音、テキスト・ドラマトゥルク=つくにうらら)であった。水中めがね∞は『有効射程距離圏外』で、「ダンスがみたい! 新人シリーズ16」(2018年)のオーディエンス賞を受賞している。今作では新たにドラマトゥルク兼出演者として、水中めがね∞の制作を担当するつくにうららが参加した。タイトルに「Ⅲ」と付いているのは、前作から3年後を意味するのだろう。端々に前作を思い出させるシーンとエッセンスが盛り込まれた本作は、タイトルが示す通り、前作との同質性と違和が重要となっている。3年という時間の経過に伴って、我々が位置する場所はガラッと変容してしまった。その実感を強く与える作品なのである。時間と場所への意識を強くすることは、すなわち我々が生きている社会へと眼差しを向けることにほかならない。本作が45分ながら豊穣なのは、連続性を感じさせる前作と併せて一本の作品のように受け取ったからである。
背景の回廊につくにが座っている舞台空間。そこにやってきた中川はまず、いかにこの劇場が耐震性に優れているかをマイクを通して述べる。壁の筋交いを自らが模して、横揺れと縦揺れに耐える様を表現した後、たとえミサイルが飛んできても大丈夫だが、そもそも日暮里なんて辺鄙な場所にミサイルを撃つ国はないと述べる。劇場を軽くイジる前説のような導入部を経て、劇場という堅牢な場所のイメージは、半年間ダラダラとYouTubeばかり見て過ごす中川の独白へとつながりる。無気力なのに、動物的本能のためかきちんと食事だけは摂ってしまう。食料が尽きてきそうだが外出する気が起きない彼女は、外部から遮断された部屋というパーソナルスペースに引きこもり、それを心理的な殻として自己を守っている。そして星を見ることが嫌いと発言した中川を受けて、なぜそう思うに至ったかをつくにが語り始める。つくにが手にした懐中電灯の明りだけが、時おり緩やかに動く中川を不鮮明に照らす。香川県の離島に友達と旅行に行った際、満点の星空を見た友達から、地球に届く光は何万年も前に消滅した星であることを聞かされた。その時、もう存在しない星のように、東京にいる家族や友人といった大事な人も、もしかしたらすでに死んでいるのではないかと不安に思った。そう感じてから星を見ないようしているのだという。エピソードを話すつくには、中川が回想するもう一人の自分なのかもしれない。地球と星、離島と東京の距離感が、別人であるのに同一人物のように見える中川とつくにの関係性にパラフレーズされている。
その後、つくにが舞台の中央にやってきて、自身の父親の話をする。脳梗塞を発症して、言語と身体機能に障害を負っている父親は、施設で暮らしている。ギャグを言うことも、好きだったギターを弾いたりロードバイクも乗れなくなった父親は、かつて自分に「後悔しないように生きろ」と言っていた。つくには、脳梗塞の原因は降圧剤をきちんと飲まなかったためとし、父親こそ後悔ばかりしてるんじゃないかと語る。今ではすっかり表情もなくなった父親だが、頻繁にスマホに送られてくる自撮り写真は笑顔のものばかり。それを見ると、別人のように感じて複雑な心境になると述べる。写真に写る父親は、過去に別の場所にいた姿である。リアルタイムで対面している時とは異なる時間と場所の隔たりが、写真の父親が別次元の人間のように錯覚させるのだろう。このシーンにも星と地球、もう一人の自分との対話といった、現在に過去がねじ込まれて混在する不可思議な感覚がある。
時間の不可思議さは過去だけでなく、現在が寸断されたり、現在に未来が混入したりもする。舞台後半には中川が不安定にくねくねと揺れたり、時にクイックを入れて力強く足を踏み鳴らして踊る。そこにかかってきた電話に出た中川が、知人らしい男性から渋谷で飲んでるから来ないかと誘われるシーン。そしてその後、つくにが誰かに宛てた手紙を読み上げ、舞台に出演した感想を述べるシーンである。前者では、今本番中で抜けられない、日暮里にいるからむしろ来てくれと述べる。当然、このやり取りも含めて作品である。それでもプライベートな時間というフィクションの現実が入り込むことで、ソロダンスを踊っている現在が中断される。この瞬間、リアルタイムの時間に切り込みが入って、より現在をくっきりと意識させられるのである。後者も同様である。楽屋に戻ってきた振付家(中川)が、ソロで四股を踏むのを忘れたと言っていた。本番に出演できて良かったという内容の手紙を、つくには舞台本番中に読み上げるのである。ここでは、未来完了の自制が現在に侵入している。以上のように時間感覚の不安定さが様々に盛り込まれているが、そのことで常に今という現在へと意識を向けさせようとする。電話の男性から、いつ終わるの?と言われて「終わるわけない」と返答する中川の言葉が印象的だ。けだるそうに答える様からは、つまらない日常が終わりなく続くという意味でのうっとうしさを感じさせられる。
©金子愛帆
中川が別のシーンで語る別のエピソードでは、そんな現在が引き延ばされる感覚が強く押し出される。例のミサイルに関する話題だ。あるダンス作品の稽古場で、子供がいるダンサーに保育所から電話があった。間もなくミサイルが飛んで来るという電話の内容を、中川は聞かされる。ミサイルは本当に飛んでくるのか。中川は逡巡する。もし本当なら、最後は踊ったまま死にたい。しかし稽古している振付家の振りではなく、今すぐ外に出て自分の踊りをしたいと思う。一方でミサイルが飛んで来なかったとしたら? 振付家に、自分の振りが好きじゃないという悪い印象を与えるし、何より稽古場を飛び出すという非常識な行動によって、仕事がなくなる確率が高い。本当か嘘かを巡って、自身が取るべき行動を稽古場に座ってあれこれと思索している内に、結局ミサイルは落ちてこなかった。日常に亀裂を入れるはずのミサイルは落ちて来ず、何も起きはしなかった。件の電話の男性には、中川は渋谷の街の人手を聞いていた。平日だからそこまで人手は多くはないが、そこそこ人は歩いていると男性は答える。東京という街は今日も明日も続き、そこには人が行き交うのだろう。劇場の堅牢さに似た何かによって守られている私たち。ミサイルや劇場の堅牢さを取り上げるのは前作にも用いられたモチーフであるが、語られるいくつかのエピソードからは、動き続ける絶対安全な東京の日常というイメージを強く喚起させる。と同時に、電話中の中川の語りからは、そこからこぼれ落ちる孤独な人間がいることを浮上させる。冒頭の引きこもりの女性は、その一人なのだ。
外界から遮断された、安心安全な東京の象徴としての堅牢な劇場空間。3年前の作品では、それを逆手に取るようにフリーダム空間にしようと試みたのである。その点で鮮明に記憶しているのが、劇場空間で中川がパンツだけのトップレスになってのパフォーマンスであった。それだけに留まらず、外部にもそれを敷衍させた。それは舞台背景に投影された映像であった。舞台背景の大きな扉は搬入口となっている。搬入口のすぐ外に設置されたカメラは、劇場関係者の駐車スペースとその先、左右に走る路地を画角に収めている。映像はカメラ前に立ってポーズを取る中川が、まずTシャツを抜いでトップレスになる様子を映し出す。そしてそのまま駐車スペースをダッシュして路地に至り、さらにいそいそとズボンを下ろした後に左に側転。さらに右側に走り去って画角から外れるまでを映し出す。劇場の周囲は閑静な住宅街だ。カメラと道路までは10数メートルの距離があるので、道路で成される様子は小さく映し出される。だが走り抜けた際に、道路沿いの住居の玄関ライトが点灯し、その直後にスーツ姿の一般男性が左側から歩いてくる姿がはっきりと映る。この男性は、中川のパフォーマンスの一部を見かけたかもしれない。
3年前の作品でこの映像を観た時は、ちょっと仰天した。この映像は何を意味するのか。劇場空間という守られた中でのフリーダムは所詮、安心安全の予定調和に過ぎず、それに飽き足らず安穏とした日常と価値観をぶち壊そうと社会への挑発行為に出たのか。はたまた、安全な東京で安穏と生きる自分自身の肝試しとして、やってしまえ精神で試みたパフォーマンスだったのか。観る者をギョッとさせるこの映像は、社会をザワつかせる攻撃的な挑発にも思えるし、悪ふざけとスレスレの暴挙とも捉えられる。そのためにかなりの振り幅がある。いずれにせよ、えいや!っとやってしまったことで生じる射程の広さにこそ、水中めがね∞の作風が凝縮されている。攻撃性だけではなく、ギャグや笑いに通じる思い切りの良さを感じてしまうのは、中川の愛嬌のなせる技なのだろう。
3年後の本作でも、この映像は流れる。つくにが父親の話をした後だ。最後まで眺めていたつくにが、「もう一回」と言うと冒頭から再生される。それを何度も繰り返す内に再生スピードがどんどん速くなり、ギャグ漫画のように滑稽に見えてくる。奔放に走りまくる中川の映像を改めて見続ける私には、もはや社会への挑発や攻撃性、あるいは度胸試し的な悪ふざけを感じることはなかった。ただただ、自由奔放に振る舞うことが可能であった3年前に感慨深くなるだけだった。この1年半の間に全世界は新型コロナウイルス禍に見舞われ、今だ収束の兆しが見えない。3年前の中川は、自由で平穏な日常秩序に亀裂を入れるべく、街中に出て暴れてみせた。しかし3年後の今は、そのように振る舞おうとする社会には、すでに目には見えないウイルスが蔓延している。もはや東京は、すっかり安全地帯ではなくなっているのである。この映像は、3年の歳月が生み出す過去と現在との大きな落差を、まざまざと突きつける。だからこそ中川が自由に暴れることの意味が変質し、恋しく感じるようにすら思えたのである。この映像は、コロナ禍前の社会と人間との関係を記録すると共に、特別な輝きすら放っていた。我々が生きるこの社会では、営業自粛という名の半強制的措置によって、職を無くして自宅待機をしている人も多かろう。中には経済苦で自殺をした人もいるかもしれない。そう考えると冒頭の中川の引きこもりは、個人的な自堕落の問題ではなく、感染症によって二次的にもたらされた、ある種の人災の被害者としても捉えられる。時間の推移を意識させることで、いかに我々が立つ場所が変質してしまったのか。そのことを東京の不穏さと生き辛さを直接的に言い立てるよりも、3年前の映像に代表される多くの仕掛けによって、観客が自ら痛感するように仕立てられている。そこが、本作の優れた点である。
ラスト、踊りを終えたワンピース姿の中川が、搬入口を開けてゆっくりと劇場の外へと消えてゆく。3年前と同様のシチュエーションが現実に再現されるのだ。ついでとばかりに観客も、舞台の上を通って搬入口から退場するよう劇場スタッフから促される。感染症が蔓延した結果、もはや劇場内外が安全ではなくなったことを改めて自覚しながら、私は退場した。きっと中川もあの時とは違った緊張感を持って、街中に吸い込まれていったことだろう。
INDEXに戻る
![]()
新型コロナウイルス感染症対策を生の舞台に取り込み、見事に対応した貴重な作品
藤原央登(劇評家)
FUKAIPRODUCE羽衣『おねしょのように』
2021年3月7日(日)~14日(日) 会場 東京芸術劇場シアターイースト
何組もの男女のペアが、作・演出の糸井幸之介によるオリジナル楽曲に乗せて、様々な愛の形を歌い語る。FUKAIPRODUCE羽衣は、そんな「妙―ジカル」の作風で知られる。類型化されたキャラクターが登場するため、観る者はそれぞれに、特定の人物が語るエピソードに心を寄せることができる。そして誰もが経験したであろう「あの時」の心情が、うまくくすぐられる。さらに糸井の楽曲が、掘り起こされた切ない感情を増幅させるのである。
この度の新型コロナウイルス禍によって、演劇は飛沫感染を誘発するということで密閉・密集・密接の「三密」対策を余技なくされている。そのことによって羽衣は、糸井の楽曲を大声で歌い上げることが封じられてしまった。去年の『スモール アニマル キッス キッス』(2020年8月、吉祥寺シアター)では、事前録音したセリフと歌を流し、それに合わせて俳優が口パクすることで乗り切った。この時はこれまでと同様のスタイルで、いかに感染対策を施して上演するかが主眼であった。今作ではそれを踏まえて、【A】【B】と2チーム体制にして出演者を少人数にし、上演手法もガラリと言えるほどに変化させた。そのことで、以前とは感触の異なった味わい深い作品に仕上がった。
本作はある冬の朝、主人公(深井順子)がやってしまった「おねしょ」から始まる。良い年になっておねしょをしてしまった主人公が、いささかの後悔と共に布団を干し、食事をしてから煙草を吸い、風呂に入り、その後に植木に水をやる。そういったささやかな一日のスケッチが、主人公の一人言と共に描かれる。そんな主人公の下に、乳母(代田正彦)、主治医(鯉和鮎美)、料理長(新部聖子)、運転手(澤田慎司)、詩人(岡本陽介)がやってくる。彼らは主人公の日常動作をその都度、介助する。そして朝を告げたり彼女を鼓舞するような歌を歌い、黒田育世が振り付けた日常動作に合わせた動きを展開する。白塗りの顔にダークな印象を与える衣装の彼らは、主人公の共感者であり支える、影としてのコロスである。その後、主人公の家にやってきた友達(西﨑達磨)とドライブにでかける。途中で野良犬に出会ってびっくりさせられるハプニングがありながらも、ピクニック場所に到着。そこで主人公は友達とかくれんぼをする。友達が鬼となり、主人公は隠れるために下手にハケるが、彼女はそのまま帰宅してしまう。時刻がすっかりと夜になった自室で、主人公は「遺書」と題される長いモノローグを吐露しながら、夜食を作り食べるなどする。朝のすがすがしさとは一転、そこからは取り巻くコロスもなしに、彼女は一人で沈鬱した気分を抱きながら床に就く。そこで再びやってきた友達が布団をめくり、誰もいなくなった床に向かって「見~つけた」と言って物語は終わる。
©金子愛帆
プロローグとエピローグとして布団による心情吐露が入るが、これが作品の奥行きを広げる大枠になっている。布団である自分はおねしょを全部受け止めてあげたいが、大きさと面積に限界がある。だから、際限なくいくらでも吸収してくれる土壌の方が適しているのでは、といった内容だ。布団の語りと主人公の行動を重ねることで、社会(布団)に包摂されない人間(おねしょ)といった構図を想起させられる。端的に言えば、社会の中で生き辛さを抱え、居場所が見いだせない人間ということになろう。いつものように朝がやってきて一日が始まる。日中は楽しく遊んで過ごしたりするが、夜になると潜在意識化に押し留めていた不安や恐怖に襲われてしまう。朝から夜の推移に伴う、気分の浮き沈み。そのことによって、時に世界から取り残されるかのように一人ぼっちになったように感じる。何でもないように思われる一日のスケッチは、永劫回帰するかのように繰り返される、現代を生きる我々の生態なのである。
終わりのない繰り返しの気分は、舞台美術からも強く印象付けられる。舞台の中央に置かれた巨大な円形舞台。上手の天井からは丸型蛍光灯のような白い美術が、だんだんと大きくなるようにいくつか設置されている。下手にも同様に、円形美術をバネのように重ねて作った浴槽が設置されているからだ。そして主人公を演じる深井順子は、飲酒と喫煙をする大人の女性でありながらも、コロスに介助されての食事や入浴時には幼児のように無邪気だ。友達は小学生のようにリュックを背負ってもいる。2チームの配役を見ると、役柄に性別の固定が特にない。場面に応じて老若男女いずれにも見える主人公に、「現代人と」して抽象化された人々がまるごと仮託されている。
飛沫のかかる距離で大人数で愛を謳ってきたこれまでの作風からすれば、今作はかなり手触りが異なっている。童話のようなメルヘンチックさは残しつつも、少ない登場人物とモノトーンの舞台表象とあいまって、まるで深井順子の一人芝居のようなシンプルな作品である。溌剌とした気分に包まれた朝は、そのプラスな感情の表出としてコロスが現れる。コロスと戯れておちゃめな一面を見せるのも、向上的な気分がそうさせる。しかし夜はメランコリックな気分に包まれるからこそ、コロスが出現できないほど内向的になる。「遺書」を語る主人公の台詞に、外出できなくなった旨の発言がある。これを新型コロナウイルス禍を受けたものだとすれば、人と人が分断され孤立することによる寂しさは、ますます高進するばかりだ。主人公のスケッチからはそういったイメージを喚起させられるが、朝と対照的な夜にはさらには死の匂いも漂っている。布団が語る土壌へのおねしょの吸収とは、永劫回帰から抜け出る唯一の方法としての死を示唆しているのかもしれない。
©金子愛帆
人間同士の接触を排した創りと死のイメージによって、本作にはどこか乾いた手触りが感じられる。羽衣の特徴であった、肉体接触を伴う性愛の表現が排されているからだ。それは下半身から放出されるおねしょと、それを受け止める布団の想像的な関係性に痕跡を留めているのみだ。しかも布団のモノローグが示すように、おねしょとしての主人公を布団は受け止めきれないと述べるのだ。それは愛の不成就であり、人間が社会からこぼれ落ちることである。だからこそ、最後に友達が発見するシーンにじんわりとした観劇感を与えられる。ささやかながらも、きっと人には確かな居場所があるはずだという安心感を抱かせるからである。そこに対個人の関係性を称揚する羽衣らしさが見て取れる。おねしょと布団が示す性愛のアイコンをクッションにし、それを介して友達が主人公を発見するシーンは、見事な感染対策にもなっている。とはいえこのシーンで、主人公と友達が直接的に出会わないことに注意を向けておきたい。友達がめくったシーツには誰もいないのだ。その前段では、隠れた主人公を友達が探すことに手間取るシーンがあった。したがって主人公が死=土壌に吸収される最期を食い止めることに間に合わなかった、とも思える。ハッピーエンドか否かが両義的に受け取ることができるラストシーン自体に、朝と夜の両極端のテンションが込められているように感じさせられた。
童話や絵本のような体裁を装いつつ、永劫回帰する世界に生きる個人を核に、様々な要素が夢のように絡まる作品であった。男女の恋愛を直情的に描いてきた作風から、観客の想像力に働きかける奥深い作品へと変貌した。この明らかな変化は、新型コロナウイルス禍の中で演劇することを模索した結果にもたらされたものだ。新型コロナウイルスの蔓延を受けて、劇場機構の感染対策はもちろん完備された。しかし作品そのものについては、オンライン配信などで対応することが多く、現下の状況を作品そのものに取り入れたものはほとんどない。そんな中で本作は、生の舞台で新型コロナウイルスの感染症対策を施し、作風そのものを変化させた数少ない例である。転んでもタダでは起きない。本作はこの劇団の新たな可能性を感じさせられた。
INDEXに戻る
![]()
「心の革命」を起こして戦後史を受け止める
藤原央登(劇評家)
TRASHMASTERS vol.33『堕ち潮』
2021年2月4日(木)~14日(日) 会場 座・高円寺1
1
久しぶりにTRASHMASTERSの作品を観た。上演時間3時間越えと変わらず長大で且つ、多彩な問題が取り上げられるので重厚である。しかしながら作品の幹がしっかりとしており、核が捉えやすい劇構造である。充実した観劇体験であった。
戦前、市民兵として南京に従軍して勲章をもらった岡本正作(森下庸之)。1980年代初頭を描く第一場ですでに、正作は寝たきりで療養している。彼は舞台上には姿を現さず、かすかに聞こえる声と引き戸越しに動く手などでうかがえるだけだ。そんな正作に変わって、保険会社の支部長を務める妻の千恵子(みやなおこ)が、家長代わりとなって家を切り盛りしている。千恵子の弟には、建設会社を営む地元の名士・西島博正(渡辺哲)がいる。大分県南部の一軒家を舞台に、岡本家と西島家の子供や孫、親類や友人を含めた総勢18人の人物が登場する。本作は1980年代初頭から2000年代初頭までを通して、一族の栄枯盛衰を描く壮大な年代記である。その過程で、両家を巡る様々な対立と問題が浮上する。作品を読み解くにあたっては、岡本家の長男・邦夫(星野卓誠)の妻・佳那子(川﨑初夏)の視点で眺めるのが分かりやすい。佳那子の成長物語を念頭に置いて勃発する問題を整理しつつ、本作の物語をこれから追ってゆこう。
2
上手から洋室のリビングとダイニング、和室の仏間と応接間が並び、さらに応接間の奥には、正作が療養する寝室がある。佳那子は劇冒頭から、千恵子から女中のように使われていることが了解される。千恵子は何かと用があると佳那子を呼び、急須の茶の入れ直しや着物の着替えを手伝うよう指示をする。親族会議のために両家の子供と配偶者が訪れる度に、佳那子は茶やコーヒーを入れてもてなす。次女の宮下紀子(安藤瞳)が嫁いでから、用事を言いつける者は佳那子しかいなくなった、と子供たちは話して気遣いはする。だが飯炊き洗濯は女のする仕事、しかも長男の妻ならば当然という女性に対する性差別が、彼らの意識にはある。一族は代々、公共事業の受注で成り立つ建設業を生業にしてきた。政治にも近い業界であるがゆえに、政治信条的にも「保守党」を支持している。だからこそ、天皇陛下の侮辱も許さない、典型的な保守主義の家系なのである。
だから千恵子は、邦夫と佳那子の子供・優人(倉貫匡弘)と尊(伊藤壮太郎)が小学校でリベラルな教育を受けており、冷戦のニュースを見て核廃絶の意義を話したりすることが面白くない。冷戦とは核を持つ国が互いにけん制して戦争を抑止することであり、大国とは核を持っている国であること。日本の非核三原則は単なる二枚舌であり、ノーベル平和賞を受賞した佐藤栄作やその兄の岸信介も、本音では日本も核を持って大国になるべきだと言っていた、と千恵子は子供たちに政治の現実を伝える。そして千恵子は、一族の人間として相応しい教育をするよう、佳那子に小言を並べる。佳那子は「学校で教えよることですけん」とおずおずと応じるしかない。しかし千恵子から外様の人間として扱われている佳那子自身も、リベラルで革新的な思想を持っている。親族内において、立場と思想の両面で少数派の佳那子は、それゆえに子供の教育や夫との離婚問題など、様々な問題に直面する。突き当たる課題に懊悩し、保守的な親族たちとの相剋を繰り返しながら、佳那子が思想を強靭に育み生き方を見つけること。その一連の過程が、本作の見所なのである。
一族の保守的で排他的な思想は、もうひとつの外部である在日韓国人・藤枝祥子(石井麗子)へと向かう。祥子は、佳那子と岡本家の次男・幹夫(阪本篤)の幼馴染である。遊びに来た祥子を、優人と尊は夕飯に誘う。だが今日は博正の市議会議員選挙の出馬にあたっての親族会議を開くので、遠慮してほしいと千恵子は伝える。それを聞いて素直に理解する祥子だが、優人たちはなぜだめなのかが理解できない。祥子の働きかけによって、千恵子が扱う保険に彼女のいとこ夫妻が入ってくれた。世話になっているのになぜのけ者にするのか。そもそも千恵子は、在日韓国人である祥子を保険に誘うことを反対していた。しかし千恵子の下で営業をしている岡本家の長女・江藤貴子(藤堂海)が、厳しい営業ノルマを前に苦戦しているために、しぶしぶ入れたんじゃないか。優人は純真な正義感から、千恵子が祥子を差別していることを暴露する。千恵子が弁を弄して祥子に説明すると、「二枚舌」に騙されるなとすら言いのける。そんな優人は、幹夫から「わりゃ黙っちょれ、腐れが」と感情的な怒りをぶつけられ、貴子の夫・江藤常広(ひわだこういち)からは胸倉を掴まれ「男がそげえ喋るもんじゃねえど」と脅される。そんな中でも優人はさらに、選挙対策を話し合うのなら、一人でも投票者が多い方が良い。だから余計に、祥子には会議に参加してもらうべきだと尚も抵抗する。そんな状況に耐えかねず、祥子は在日であるが故に、自分には選挙権がないことを優人に説明する。なぜ日本で生まれて、日本語しか話せないのに選挙権がないのか。大人たちに必死に問う優人であるが、誰もそれに答えられない。優人の考えに共鳴する佳那子は、博正の選挙公約に在日韓国人への選挙権を盛り込むように提案すると祥子に伝えて、その場はひとまず収まる。
かつて祥子は、高校卒業と共に長崎に行く幹夫を追いかけようとしたことがあった。しかし千恵子から交際は許すが、結婚は認めないと告げられて断念した。その大きな理由も、祥子の出自を忌避する千恵子の考えと、それを振り切ってまで一緒になることに踏み切れない、無自覚に差別に加担した幹夫にある。彼らは見得や世間体を取り繕い、女性や在日韓国人を無意識に差別するが、そのように振る舞うのはこの一族だけではない。その元凶には先の戦争の敗戦を受けて、戦後をいかに生きてきたかという日本人の問題がある。差別問題や保守と革新の対立などは、敗戦を正しく受け止めなかったことにあると後々、佳那子によって喝破されることだろう。岡本・西島両家が女性や在日韓国人に向ける眼差しは、その脈々と流れる体勢の文化が個々人に習慣化した結果の、ひとつの顕れに過ぎないのである。佳那子を筆頭に、優人や尊、そして博正の姪で佳那子の友人・西島光江(清水直子)は、本作で旧弊に位置付けられた保守思想に染まった親族たちと抗い、時には革新的な考えに説得することに成功してゆくのである。
3
しかしそれを達成するためには、佳那子は大きな障害を乗り越えねばならない。その一つが、佳那子と優人、そして邦夫との教育と夫妻問題である。先述したように、千恵子は優人と尊の教育に不安を抱いている。子供たちはこれまで一族の中では疑問にすらならなかった、差別の構造を明らかにして突きつけるからだ。その要因は、毛嫌いする「革新思想」を学んでいるからであり、それを教える社会党の教師ばかりいる学校と佳那子の教育が悪い。そのように千恵子は思っている。その表面化のひとつが第三場で描かれる、優人が学校から持ち帰ってきた平和学習プリントを巡る問題である。プリントには、南京事件に関わった正作に意見を聞いて学びを深めようと記されていた。折しも西島家には、マスコミから南京大虐殺についての取材が多数寄せられており、それに閉口していたところである。そんな中で、優人はプリントに従って正作に南京事件について質問し始めたため、千恵子は激高する。千恵子は、かえって事態がこじれるという優人の嘆願を振り切り、学校に苦情の電話を入れる。千恵子は校長に直接抗議をし、謝罪を勝ち取ったと誇らしげに報告する。
そんな千恵子からの教育に対するプレッシャーが、佳那子を追い詰めることになる。優人の左腕にある大きなあざを見つけた家族たちは、連日のマスコミ取材と平和学習プリントとを関連付け、学校でいじめられているのではないかと心配する。優人は転んでできたと説明するが、実は佳那子が殴ったためにできたものであることが判明する。優秀だった千恵子と邦夫のように子供を育てなければならない。そう駆り立てられる佳那子は、95点のテスト用紙を隠していた優人を応接間に追い詰め、激しく怒る。「なし、こげなんも出来んのか。情けねえ」と佳那子は優人を殴るのだ。佳那子をそう駆り立てるのは、保守的な西島家の、それも長男の妻という意識が原因となっているのだろう。母として、そして妻としてきちんとあらねばならないというプレッシャーが、子供の虐待となって表面化するのだ。それほどまでに、彼女は追い込まれていたのである。地方に根強く残る封建的な家父長制度に一族は捉われているのだが、それを本来体現するべき正作が寝たきりとなっており、半ば不在である点がポイントである。その不在を千恵子が埋めているのだが、あくまでも代理であり疑似的であるからこそ、立派な家父長を実現しようと、苛烈に振る舞うのである。だからこそ1980年代時点では佳那子も、千恵子のようなミニ家父長たらんとするのだ。この構図は戦争責任を免れた昭和天皇と、森に囲まれた皇居が「中心の不在」の象徴と指摘されたことと通底する。責任の主体を曖昧にしたまま、戦後の日本は家父長制を維持したままに、戦後復興と高度成長を成し遂げた。本作では改めて、家制度とそれを保持するに至った源流=戦後史が問われるのである。
教育を佳那子に任せ、自身は家庭内で「不在の中心」になっている邦夫は、建設機械の営業職をしている。邦夫は仕事の接待で連日、帰りが遅いばかりか浮気をしているらしい。そのことを佳那子は、邦夫が密会しているホテルに、相手の女性の家族を装って確認して突き止めたと光江に話す。第三場では邦夫の浮気と離婚を巡って、千恵子と邦夫、そして実家から赴いた佳那子の母・尾上久子(石井麗子)を交えた話し合いが持たれる。建設機械は生活必需品とは違い、接待を重ねて契約を取る必要がある。それも仕事であり、浮気は誤解であると邦夫は弁解する。邦夫の煮え切らない返答に、久子は佳那子が離婚したいと言えば止めるつもりはないと告げる。離婚されれば、西島家の長男は「人並みの」生活もできないと世間から後ろ指をされるとして、反対する千恵子。佳那子は、「人並みの」生活に西島家がこだわるのは、正作が南京に従軍した件で注目を集めているため、世間体をつくろうことに敏感になっているからだと久子に伝える。佳那子のその言葉を受けて、千恵子は世間の注目を浴びていることが関係して、優人が学校でいじめに遭っていると久子に報告する。久子は優人に、誰にやられたのか教えてほしいと嘆願し、千恵子はいじめに抗議すると再び学校に電話をしようとする。そこで佳那子は、自分が殴っていたことを告白して自身の虐待が判明するのである。「子供に手えあげるんなんか、最低の人間がすることど」「尾上家の恥さらしが」と、佳那子は久子から非難される。そして千恵子と邦夫は優人に、テストで100点取ることは当たり前で、優人も悪いと告げる。優人はそうやって母親を追い詰めるから叩かれるのだと告白する。一連の様子を聞いていた尊は邦夫に、虐げられている母親が少しでも楽になるように、優人は我慢して叩かれていたと述べる。それを聞いて佳那子は慟哭する。尊から離婚しないでほしいと言われ、邦夫からは浮気は否定するが酒席を控えて早く帰宅する約束を取り付ける(後にそれは嘘であり、世間体のために離婚だけは避けたことが示唆される)。それによってなんとか離婚は回避されるが、この出来事を契機に彼女は優人に、子供たちが成人したら家を出ることを決意するのである。
4
本作で最大の対立は、政治に関わることである。先述した一族会議で、博正が市議会議員選挙に出馬することが発表される。その理由は、公共事業を西島建設に受注させて会社の経営を立て直すためである。確実に当選するため、定年に伴う千恵子の退職金と貯金を選挙資金に充てることが告げられる。自宅購入のために千恵子の財産をあてにしていた子供たちは寝耳に水であった。加えて、地元企業に金を配って票を買うことにも、西島建設部長で博正の甥・西島新吉(長谷川景)を筆頭に反対する。そういった意見を、当選して西島建設がトンネルの拡張工事を受注すれば、千恵子に金が返せる。もし落選しても、自宅購入費の半額は補償するなどと、博正は一人ずつ切り崩してゆく。しかし佳那子が祥子と約束した外国人参政権の付与を政権公約に盛り込むことは、却下される。博正の息子で西島建設専務・西島健介(森下庸介)が、波風が立つ公約を掲げれば、保守層の離反を招くと主張したからだ。博正に代わって社長に就任する健介は、まだ20代で未熟である。新吉は、実質的な経営者として健介の右腕になることが決まっていた。だが贈収賄に手を染め、市民のための政治を志さない博正のやり方に納得できない新吉は、会社を退職すると告げて席を立つ。
選挙に当選した博正は、公約通りにトンネル工事の受注を始め多くの公共事業を自社に斡旋し、会社を立て直す。トンネルの拡幅によって自転車道ができたことで安全性が増し、町民からも大きく尊敬される博正は、三期目の選挙を控えるまでになっていた。1990年代初頭を描く第四場では、博正が挑む三期目の当選を阻むべく、新吉が対抗馬として出馬する。新吉は西島建設を辞めた後、セメント工場で労働組合の幹部をしながら、革新政党と共に市民を交えた様々な勉強会を開いていた。そんな新吉が出馬する理由は、新吉が懸念していた博正の金権政治がエスカレーションしていたからだ。博正は地元の建設会社と談合し、公共事業を高値で落札しつつ順繰りに工事を各社に配分していた。腐敗した政治を主導する博正に、正常な民主主義政治を取り戻すべきだと新吉は主張する。博正は工事を高く落札することで、すそ野が広い従業員にまで給料が払え、建設業界全体が潤うこと。新吉が言うように自由な入札を許せば、他の地域に金が流れて町が発展しないと応じる。再び親族会議が開かれるが、今度は千恵子以外の支持を博正は失う。保守思想によって場が支配される第一場とは逆転し、しだいに家族たちは革新思想に理解を寄せ始める。当初は博正に不出馬を求めた新吉だが、交渉は決裂。両者が出馬するという一族での骨肉の争いの結果、博正は落選してしまう。2つの親族家族会議が成す対照は、鮮やかで印象深い。
そんな新吉は2000年代初頭の第六場では、博正の記録を越えて三期目の当選を果たして議長となっている。皮肉が効いているのは、成人して東京で劇団活動をしている優人が構想を温めている作品で、新吉もまた腐敗政治に足を突っ込んでいることが暴露されるからだ。資本家が富を独占するのではなく、労働者の待遇改善を訴えるど、弱者救済のために新吉は議員になった。だが今や、自分の息子を市役所に就職させるために口利きをしていたのである。2000年代に入っても、今だに外国人参政権は認められていない。改めてその件を進めるように新吉に依頼する佳那子。新吉は「忘れてはいない」と答えるが、彼も結局、保守政治家の一人に堕ちるのである。
5
ここまで、対立に絞って本作を観てきた。本作でなされる対立や差別の数々は、保守と革新のイデオロギーが、個人の意識に根差した結果として起こったものである。このイデオロギー対立はなぜ起こったのか。本作で示される答えは、第二次大戦の敗戦を戦後の日本人が正しく受け止めなかったからとされる。敗戦した事実を直視できず、日本人は経済分野にステージを移して戦い、そのトラウマを払拭しようとした。確かにそのことによって、戦後の目覚ましい復興は成し遂げられたかもしれない。しかしその過程で、業界が結託して利益誘導し、税金を不当に利得する談合政治が横行するようになった。そしてそれを、義理と人情という美名で糊塗し、一部の業界と資本家といった「村」だけが得をする構造を作ってしまった。市民や国民を無視した業界政治は、誤った戦争に突き進んだ間違いを方向転換できずに多数の国民を死に追いやった、先の大戦の構造と同じではないか。そのように本作では規定されるのである。
金に捉われているのは博正だけではなく、千恵子の子供たちもその金をあてにしていた。それを目当てに、金権政治を行おうとする博正に従い、投票して手を貸すことも厭わなかった。そんな金に執着する心性がもたらす悲劇が、第四場における長女・貴子の借金問題である。貴子は保険料を自己負担することで、契約ノルマを達成させるという愚挙を犯していた。土地の購入資金のほか、何度も資金援助を受けている千恵子にはすでに頼れなくなり、サラ金から何社も金を借りていた。借金総額は1000万以上。支払いが苦しいからといって、大量に解約すれば営業所にバレてしまうのでできない。貴子は見栄やプライドが邪魔をして、誰にも相談できずに引き返せなくなってしまったのだ。そのことを聞かされた常広は、家のローンが20年以上も残っていることを悲観。発狂して応接間の日本刀を手にする。これで自殺に見せかけて殺し、保険金で借金を返せと常広は貴子に頼むのだ。そんな二人に、佳那子は自己破産を勧めて彼らを救う。この時点では佳那子も、保険営業の仕事で自立を模索し始めていた。そんな佳那子と光江は、新吉と革新政党が開く勉強会に出入りしていた。彼女たちはそこで知り合った弁護士から自己破産を知り、借金があった光江も助けられたのである。自らの立場と思想を確立しようとしていた佳那子は、邦夫に対してお茶汲みをする女給であることを拒否し、家を出ることを了承させ、そして新吉の出馬を支持するよう説得する。そして自分に任せておけば再び「満ち潮」が来ると、選挙への支持を取り付けようとする博正に、生き方を変えななければ潮が堕ちっぱなしの「堕ち潮」になって、日本は取り返しがつかない状況になると迫る。佳那子は強く自己を主張するまでに成長していたのである。
6
誤りを正すことができないくらい、個人にまで深く浸食した保守イデオロギー。それを変革しなければ、最終的に人生を崩壊させるまでに至ってしまう。冷戦とバブル期のただ中で、戦後の敗戦を払拭したかに見える1980年代以降の日本を描く本作は、その長大な時間軸に見合う壮大な視点がある。そこから脱するにはどうすれば良いか。そのキーワードとして、「受け止める」「和解」「心の革新」が示される。
繰り返すと、千恵子や博正が保守イデオロギーを脱却できないのは、敗戦を受け止められないからだと佳那子は述べた。物事から目を避けずに受け止めることの重要性を、佳那子は優人の生き方から学んだのかもしれない。優人もまた、その姿勢を光江の息子・西島智巳(小平伸一郎)から教えられた。第三場で優人は光江に、智巳の父親は死亡したのではなく、生きていると聞いたと告げる。離婚して別の家族を持っていると優人に説明した光江は、これは智巳のためについて良い嘘だから黙っていて欲しいと頼む。その一連の会話を影から聞いていた智巳だが、実は彼もそのことを大人たちの会話を通して知っていたと言う。改めて真相を知っても普通に振る舞う智巳に、胸のつかえが取れてかえって良かったと光江は安堵する。そこで優人は、父親に会いたくないのかと智巳に尋ねるが、「大人やけん」と受け入れていると答える。大人びた智巳の考えに触れて、優人は受け止めることの重要性を知る。だから南京大虐殺に正作が関わっていることを感情的に否定する紀子に、歴史を認めなければならないと言ったり、邦夫と佳那子の離婚に賛成するのである。
©ノザワトシアキ。
佳那子と共にリベラル思想を堅持し育んだ優人は、2000年代初頭を描く第六場では、先に触れたように東京で劇団活動をして自分の人生を歩むようになっている。弟の尊は、千恵子が嫌っていた教員になった。そして佳那子は約束通り、邦夫とは籍を入れたまま別居をしている。博正はすでに亡くなっており、千恵子は痴呆が始まって応接間で寝たきりになっている。千恵子の介護のために、貴子と常広、光江がたまに顔を出す状況だ。西島建設を倒産させた健介は、博正の知り合いの会社に拾われている。健介は博正に代わって千恵子からの借金を返しているが、薄給のために二万円ほどしか工面できない。そのためために、千恵子から「おちょくっちょるんか」と突き返されしまう。
そんな中、優人の4年ぶりの帰省に合わせて、久しぶりに佳那子も顔を見せる。佳那子や光江に力なく悪態をつく千恵子だが、記憶が混濁する中で、正作を追ってかつて満州に行ったこと、戦禍の中で長女とはぐれて死なせてしまったことを詫びる。その娘の名前が叶(かな)であることから、佳那子は初めて千恵子と会った際、死んだ娘の生き返りだと喜び、「カナちゃんと」呼ばせてほしいと言われたことを思い出す。千恵子が幻視した光景は、正作が南京事件に関わった際に起こった出来事なのかもしれない。正作を追いかけた健気さや娘を亡くした悲劇は、これまでの傍若無人な千恵子像との大きなギャップをもたらす。亡き娘を介して佳那子と千恵子がつながることで、2人の関係性に奥深さが出る。そのために、しんみりとした味わいをもたらす良いシーンである。一方で千恵子は、他国へ侵攻する南京大虐殺に関わっていたことについては、タブー視して否定してきた。そのことを鑑みれば、自分たちの家に関係することだけはしっかりと記憶し、甘美なものとして抱き続けることに対する、保守主義者の身勝手さもここからは感得できよう。
そのような顔見せがあった後に、佳那子と邦夫は久しぶりに正対する。邦夫は佳那子に、千恵子はもう長くなく、食事の用意をしてくれていた尊が県北の学校に異動になる。広い家に一人ではあまりにも寂しいため、昔のような過ちはもうしないから戻ってきてほしいと告げる。その言葉に騙されるなと、かねてから主張してきた離婚を勧める優人に、佳那子は千恵子が亡くなったら考えると邦夫に応じる。争いは人の憎しみから生まれる。一人ひとりが憎悪の心を理性で沈める心の革命を起こさなければ、いつまでも対立はなくならない。新しい未来を切り開くためにも、まずは自分から和解へと一歩踏み出す。そのように佳那子は宣言し、邦夫を許すのだ。
第一場から20数年が経過する第六場では、千恵子はもちろんのこと、他の登場人物も腰が曲がって白髪が目立ち、発話がゆっくりとなっている。だが佳那子と光江だけは、第一場と同じく若々しい容貌のままだ。時間と共に老いてゆく人物は、時代の推移と共に堕ち続ける日本の反映である。国の趨勢に抗って自ら考え、主体的に生き方を模索してきた佳那子と光江の人生は、これからも明るい。本作が込めたメッセージが、演劇的に明瞭に視覚化されていた。一年以上に渡る新型コロナウイルス禍の最中を生きる中で、我々は提唱されたニューノーマル(新しい生活様式)の実践が求められ、自粛警察を始めとする様々な分断と対立を日々、目の当たりにしてきた。本作は敗戦を受け止め損ない、経済戦争に邁進してきた戦後日本と、それを支える保守イデオロギーの趨勢を描いてきた。そのことはまさに、コロナ禍をいかに受け入れて、社会構造を転換するかという現状と重なる。この一年で、経済活動を活発化させるために元の生活に戻そうとする側と、新型コロナのゼロリスクを求めて感染を徹底的に抑制しようとするもう一方の側との分断が生じている。そんな今こそ状況を正しく受け止めて、心の革命をひとりひとりが起こして和解へと歩み寄る必要がある。佳那子の成長物語は、観る者にそう思わせる説得力があった。
7
これまで述べてきたように、本作はイデオロギー対立を内面化した個人の葛藤と超克を軸としているため、劇構造の骨格が明瞭である。そのために観る者に力強く迫ってくる。それを支える俳優たちの存在も大きい。TRASHMASTERSの劇団員たちは、生活感を滲ませた人物を立体化する俳優たちだが、客演の渡辺哲、みやなおこが加わって、一族の大河物語により厚みが増した。博正の選挙演説シーンでの渡辺哲は、田中角栄にも見え、豪快な政治家像を造形した。底意地が悪いみやなおこ演じる千恵子は博正と共に、あらゆる場面で激高し、恫喝によって家族たちの異論を封じる。その様には凄みはあるものの、あまりにピントがズレていることを頭ごなしで主張するため、むしろ笑わせられる。それ以外にも、会話の中で笑いを誘うやり取りが散りばめられている。例えば第一場での、緊張感溢れる一族会議を例に取ろう。光江は千恵子にラーメン屋の開店資金を出資してもらったが潰してしまい、借金を返すべく内職をしながら西島建設の事務員をしている。千恵子が博正に資金協力することに反対する光江に対し、「お前がラーメン屋潰さんかったら、こげなことになっちょらせんのじゃあ」と切り返して、光江を苛立たせる。そのような間の良い突っ込みによって生じる笑いが、さもしい戦後日本人を浮かび上がらせることによ寄与しているのである。TRASHMASTERSの舞台で、これほど笑わせられるものはなかった。この劇団に喜劇的要素があったのは発見だった。
最後に、『そぞろの民』(2015年)との対比を記しておきたい。日本家屋を舞台に、イデオロギーを背景にした家族の亀裂を描く点では、2つの作品は似ている。『そぞろの民』では最後、正義を貫こうとする人物が自殺して終わる後味の悪いものであった。登場人物を自死させることで現状の悲惨さを強調しつつスキャンダラスに劇を盛り上げ、加えて観客を挑発もする趣味の悪さに、私は批判的だった。そうするしか当時の中津留は、落としどころがなかったのかもしれない。しかし本作では、佳那子の生き方を通して、死を迎えることのないオルタナティブな人生を観客に提示してみせた。それは中津留が『そぞろの民』から思考を深めた結果であろう。だからこそ時間に逆行して若々しくなる佳那子と光江の姿が、一種の清涼感や瑞々しを惹起させたのだ。『そぞろの民』と対比させると、意義深さがなお一層増す作品であった。
※セリフの引用は上演台本より
INDEXに戻る







