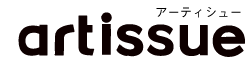 |
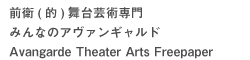 |
劇団青年座『コラボレーターズ』イリュージョンとしての政治と芸術
藤原央登
(劇評家)
しかし2011年に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所事故という、国家的大惨事と人災に直面したことで、日常生活への差し迫った危機感に気付き、〈社会派〉の作品に取り組む演劇人が増えて観客も支持した。その傾向は、当時の第二次安倍政権の諸政策への反発となってさらに加速した。その結果、新劇団と小劇場演劇の作家が共同創作し、同時代の問題を劇化する作品が注目されて両者の垣根がなくなり始めた。上演される作品もイデオロギーや主張が全面に押し出されるものではなく、小劇場演劇が積み重ねてきた様々な手法の実践の取り入れや、市井の民の目線で細やかに社会を見つめる物語が生かされている。世界各地で戦争が勃発し、選挙や政治体制において民主主義の危機が指摘される昨今、関心を呼ぶ〈社会派〉の作品はこれから先も充実してゆくことだろう。
 ©坂本正郁
©坂本正郁
劇団俳優座の準劇団員たちが1954年に結成した劇団青年座は昨年、結成70年を迎えた老舗新劇団である。旗揚げからの理念である日本の創作劇を主に上演し、日本や世界の同時代を見つめる作品を上演してきた。ベテランから若手まで幅広い俳優が在籍するが、上演に接して感じるのは、劇団名通りに若々しいことだ。演技が上手いだけでなく、ナチュラルに笑いが取れる俳優陣の魅力が、若々しさの源泉となっている。そのことは、3月に上演した『Lovely wife』で10年ぶりに劇団本公演に出演した、高畑淳子のコメディエンヌぶりを見て再認識させられた。彼女の放つ空気感が、劇団員に浸透しているのだ。
そんな青年座は昨年度の劇団創立70周年記念公演を終え、また西池袋にある舞台芸術学院の閉校に伴い、そこを新たな本拠地に新たな歩みを始めた。それに見合うように、2025年度1本目には珍しく海外の戯曲に取り組んだ。映画『トレインスポッティング』の脚本で知られる、イギリスの劇作家・ジョン・ホッジが2007年に執筆した作品である。ロシアの作家でソビエトの政治体制に批判的だったあるミハイル・ブルガーコフと、ソビエト連邦共産党書記長(最高指導者)だったヨシフ・スターリンの関係が軸の本作は、芸術と政治の関係や、独裁者の思想とそれによる民衆の圧制が描かれる。芸術が社会に翻弄される様は、新型コロナウイルス禍において演劇や映画といったエンターテインメントが不要不急として批判されたことが記憶に新しい。そしてソ連を工業国化するために、一国社会主義論を掲げて中央集権と恐怖政治を敷き、政敵や反政府的な人物を粛清するスターリンによる「スターリニズム」と呼ばれた政治体制は、権威主義国家の台頭が懸念される昨今の状況下では現代に響く重みがある。ブルガーコフとスターリンの知識がなくても、彼らの思想と政策が分かりやすく伝えられる本作は、歴史に材を採った〈社会派〉作品である。しかし教条的にテーマを押し付けるのではなく、エンターテインメント要素が盛り込まれたユニークな作品となっている。演出と演技もそれに寄与しているが、その最大の要因は、ブルガーコフの仕事をスターリンが、スターリンの仕事をブルガーコフが担うという戯曲上の仕掛けが大きい。互いの立場を交換するという趣向は、物語上における登場人物間の相互理解だけでなく、役を演じるという演劇の本質を題材にしているとも言える。そういう意味でも本作は、舞台表象が意味を持つという、小劇場演劇の蓄積を感じさせる作品となっている。
劇冒頭から意表を突く。ブルガーコフ(久留飛雄己)と妻のエレーナ(松平春香)が寝るアパートの一室。奥の部屋に続く木の引き戸が開くと、スモークと閃光を背景に、オールバックで口ひげのスターリン(横堀悦夫)が、『サタデー・ナイト・フィーバー』のジョン・トラボルタのような決めポーズをして現れる。起き上がろうとするブルガーコフの片腕をエレーナが掴むが、彼はそれを振り切ってスターリンの元へと引き寄せられる。だが一転して、ブルガーコフはスターリンに追いかけられて部屋中を逃げ惑うが、最後に掴まってしまう。悪夢のような導入部分が、物語を象徴的に視覚化している。
反体制思想を持つブルガーコフは、戯曲『モリエール』の上演初日を迎えるが、当局によってその後の公演を中止に追い込まれてしまう。同僚のステパン(鹿野宗健)を伴う秘密警察・ウラジーミル(小豆畑雅一)が、ブルガーコフに交換条件を提示する。それは4週間後のスターリンの誕生日に合わせて、彼の青年時代の戯曲を献上して喜ばせれば、『モリエール』の上演を許可するというもの。ブルガーコフは、友人の若い作家・グリゴリー(君澤透)には、芸術的抵抗を貫徹するようアドバイスしてきた。エレーナや家に出入りする、農園を所有する元貴族・ワシリー(加門良)とその妻で教師のプラスコヴヤ(宮寺智子)に反対されつつも、ブルガーコフは自作の発表の機会とを天秤にかけて執筆するか否かを悩む。そんなブルガーコフの自宅に一本の電話がかかってくる。その声の主はスターリンであった。スターリンはブルガーコフの思想は受け入れられないが、天才的な文体に惚れ込んでおり、『白衛軍』は何度も劇場で観劇したという。そして直々に手を差し伸べるとのスターリンの言葉に言われるがまま、ブルガーコフは地下通路を進む。そこは、クレムリンの執務室の真下にスターリンが設けた、誰にも知られていない秘密の小部屋であった。そこでブルガーコフとスターリンは対面する。
若い頃に詩を書いていたというスターリンは、膨大で煩わしい共産党書記長の職務から解放されたいと言い出す。そこで、執筆を逡巡するブルガーコフに代わって、スターリン自らが自身の半生を戯曲化する代わりに、ブルガーコフに共産党書記長の職務を代行するよう依頼する。以来、秘密の小部屋を仕事場とし、喜々としてタイプライターを叩いて執筆するスターリンの傍らで、大量の書類に目を通して「ヨシフ・スターリン」の署名をするブルガーコフという、役割を交換した奇妙な協働関係が始まるのだ。少しずつ書き上げられる戯曲をブルガーコフがウラジーミルに渡すと、すぐさま劇中劇として稽古が始まる。靴屋の息子としてロシア帝国下だったグルジアで生まれたスターリンは、首都トビリシの神学校に入学。彼はやがてマルクス主義者となり、教師に反抗した。また革命運動で逮捕された際は、監獄で看守にいたぶられても耐えたことなどが演じられる。どれだけ身体に攻撃されても、心は自由でいることの重要性を説くスターリンの言葉は、圧政化でのブルガーコフ自身の創作態度と通じる。そのような発見も手伝って、ブルガーコフはスターリンに共感してゆき、共同作業によって同士的な関係を築くようになってゆく。スターリンからヨシフと呼んでくれと言われたブルガーコフが、思わず腕をこずきながら彼の名を呼んでしまい、両者が戸惑いながらも受け入れる場面はその典型だ。ブルガーコフは時にスターリンに執筆のアドバイスをしながら、共産党書記長の仕事をこなしてゆく。その働きによって、ブルガーコフには運転手と車が付き、アパートにはお湯が通るなど一家の生活環境も劇的に改善されてゆく。威厳のある独裁者に似合わない、人間味のあるスターリン。そして、当初は反発し戸惑いながらも、彼の魅力に引き寄せられて人間的な心の交流を通わせ始めるブルガーコフ。意表を突く舞台設定が生み出す両者のやり取りが、本作の最大の魅力となっている。真面目な社会派劇だと思っていたために、両者が醸し出すおかしな雰囲気に笑って良いのか戸惑うほどであった。スターリンとブルガーコフの関係性は、戦時下の日本の取調室を舞台に、検閲官と劇団の座付作者がいつしか最高の喜劇を共同で創り上げる、三谷幸喜『笑の大学』を彷彿とさせるほどだ。笑いの要素は他にも散りばめられている。例えばウラジーミル。彼は昔、演劇をかじっていたことを理由に、劇の上演に向けてプロデューサー兼演出家を進んで買って出る。終始無言でブルガーコフ一家を監視するステパンを従え、躊躇なく人を殺すウラジーミルが演出に乗り気で、出来上がった戯曲に興奮する様も、ギャップを生んで笑いを生み出す。スラップスティックのようなあり得ない展開を導入した意外性のある戯曲に取り組み、沈鬱な空気を破って不謹慎な笑いを生み出す俳優たちの力は相当なものだ。俳優全員がしっかりとした発声と押し出しの強い演技をしつつ、隙のある魅力的な人物像を造形し、充実したアンサンブルを見せた。青年座の俳優の底力が詰まった出来だと言えよう。
重いテーマにブラックな笑いが胚胎する本作だが、劇後半に至り、芸術を人質にとって政治に絡め取る本質が露呈する。緊張感を緩めてコメディ色を強くしつつあった雰囲気が、再度恐怖へと振り子が揺れるのである。書記長の仕事を代行するブルガーコフは、国家の統計データが赤裸々に記された大量の書類を処理する過程で、職務上の問題に直面する。ソ連では重工業を中心とした工業化への移行と、農業の集約化による生産物の国家管理を柱とする五カ年計画が、1928年から逐次計画され実施された。それに関連して、農地での食料の生産が少ないため、都市部で働く工員に食料を生き渡らせることができないという問題が浮上する。スターリンに意見を求めながら、ブルガーコフは問題の解決を図ろうとする。農家も来年の作付け分と、自らが食べる分を確保しなければならない。農家と都市部の双方が、食糧問題で逼迫しているのだ。しかし工業国化という国家の目標は喫緊の課題である。したがって、限りある資源を農民から奪って都市部に分配する必要がある。そのような結論にブルガーコフは至り、スターリンの署名をする。その決定によってワシリーの農場から食料が簒奪されてしまう。不満を漏らすワシリーに対しても、ブルガーコフは仕方がないと冷淡な対応を取る。ここで重要なのは、ブルガーコフがスターリンと会話をする内に、自らが市民を犠牲にする答えを導き出す点である。ブルガーコフがスターリンの名で強権的な政策を実行したために、スターリンに不満が向けられる。だがブルガーコフは、国家を率いる者の苦労を吐露するスターリンの気持ちを理解してしまう。舞台前半では役割を交換することで互いの仕事を相対化し、その上で心を通わせる人間関係の意外さが笑いを生んだ。しかし同じプロセスは後半に至って、ブルガーコフが進んでスターリンの独裁政治に取り込まれ、推し進める役割を負ってしまう。それに伴って共同作業の比重も、戯曲執筆から独裁政治の遂行へと大きく傾くのである。
そんな折、スターリンの失脚を狙う告発文が出回る。意見を求められたブルガーコフは、怪しい者を審問してみてはと提案する。そのターゲットになったのが、ワシリーとプラスコヴヤであった。ワシリーはソヴィエト政権樹立に貢献した、レーニンが率いた組織・ボリシェビキの党員であった。だが農作物を奪われたことへの恨みを持っているはずだ。また、革命政権前のロシア帝国時代を知っている彼は、そこへの回帰を志向しているに違いない。そもそも、農地を持つ者は社会主義に反する特権層であり、その妻も同様であるとの理由で粛清されてしまう。審問は一度行うとキリがなくなる。疑惑者が次々と現れて、誰が裏切り者なのか不信の塊になったスターリンはエキセントリックに暴れ、全国各地の書類を一枚一枚しらみつぶしにチェックしてあぶり出すと言い出す。審問にかければ問題が解決するとの提案に乗ったのに、事態はさらに悪くなったとスターリンに詰め寄られたブルガーコフは、一軒一軒調査していては効率的ではない。土地をブロックに分けて、審問者数をあらかじめ割り当てる「システム」の導入を提案する。反体制思想が集団化することを防ぎ、個人をバラバラに分断することで協力できなくすることが狙いである。これに大いに共鳴したスターリンは、ブルガーコフに署名をさせて大粛清を始める。スターリンの半生を記した戯曲は、ブルガーコフの名で世に出されることになる。そのことを、反体制派の一級芸術家・ブルガーコフすらスタリーンにおもねったという証拠にして、独裁政権を推し進めること。すべてはスターリンの狡猾な計画であり、ブルガーコフはその術中に嵌っていたことが判明する。
スターリンは、人民服のポケットにパイプを入れており、事あるごとにそれを取り出して吸う。だがパイプから煙が出ていないことを、ブルガーコフはまがい物だと指摘する。それに対して「イリュージョンだと」言ってのけるスターリンの言葉こそ、本作を象徴する台詞である。そのことは、ブルガーコフが書類にスターリンの名をサインをするだけで、政策が実現してしまうことと同義だからである。大粛清の嵐を目の当たりにして、ブルガーコフはそこまでを意図していないと、スターリンに中止するよう詰め寄る。スターリンは言葉ではブルガーコフの要求を呑むものの、事態は改善しない。なぜならば、すでにスターリンの名でGOが出されてしまっているからである。大多数の人間の処刑という一人の為政者の政策が、書類にサインをするだけで実行されてしまうことは、虚構の物語を作家の名で書籍として出版することと、イリュージョンの現実化という点で通じる。つまり、政治も芸術と同じくらい虚構を含んでおり、表裏一体である。だからこそ、スターリンの署名は別に本人がする必要はない。重要なのは、その名前が書類に書かれることだけにあるのだ。ブルガーコフは1940年に、腎硬化症によって48歳で死去する。その際、ブルガーコフ家にかかってきた電話を取ったエレーナに、スターリンが「同士」として悼むラストシーンは、両者が一対であったことを知らしめて後味の悪さを残す。権力者の名前が記された言葉が現実政治を動かし、しかもその署名は本人ではなくても実効性を持ちうるという問題は、AIを使って政治家や有名人の画像や音声を加工して当てはめた、フェイク動画が氾濫する現代においてこそ切実である。それだけでなく、同一の偽情報を大量に投下することで、たとえ発信者が匿名であっても真実であるかのように思わせる、情報の洪水がもたらす危険性も指摘されている。知らぬうちに世論が形成されたり左右されたりする現代においては、政治に芸術が利用されること以上に、国民生活そのものが取り込まれ得る。歴史を題材にした恐怖のコメディは、改めて政治と日常の近さを観客に突きつけた。
食卓パーティー時にシャンデリアが下りると共に粉雪が降ったり、劇中人物が粛清されるたびに白い防水シートにくるまれた骸が下りてくる。天井が高い吉祥寺シアターの空間を処理する演出が巧みであった。古びたアパートの一室は様々なシーンに変貌するが、何よりもスターリンの登場シーンには、扉を開ければ朝鮮海峡や満州の光景が出来するアングラ演劇さながらの演出であった。そう思えば笑いと恐怖がない交ぜとなったナンセンスな舞台設定も、アングラ演劇以後の作風の精神が流れている。本作は新劇と小劇場の垣根を超えた〈社会派〉作品の、近年の特徴があますところなく認められる作品であり、そのアプローチを一段階高めたと言えよう。
関連記事
「夢うつつ」の世界と対峙するために――2023年演劇回顧
退廃的な秘儀から溌剌としたバトルへの転換―『再生』が孕む演劇的な意義を改めて考える―
ハイバイ『再生』
INDEXに戻る