
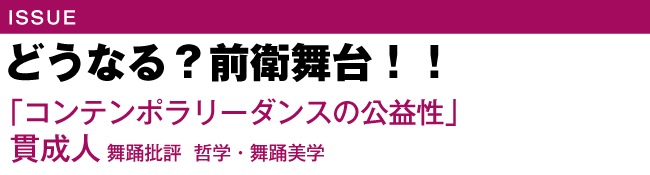 たまたまダンスのワークショップに参加する羽目に陥ったとき、だれかに動きを押しつけられると抵抗を感じるが、かといって、いきなり「自由に動け」と言われてもなにをしていいかわからない。鷲田清一によると、自分の好きなように動くよう迫られて進退きわまった挙げ句、ついにラジオ体操を始めた大学教授がいたという。 この二律背反を解消するのがコンテンポラリーダンスである。「背中合わせで立って相手の力を利用して動く」「目をつぶって、合図なしに、気配だけで、10人同時にしゃがんでみる」など、コンテンポラリーダンスのワークショップ技法は、各自の動きを知らず知らずのうちに引き出し、参加者は、負担なく自分を発見することができる。文部科学省学習指導要領改訂にともなって、24年度から必修化されたダンス授業にも応用可能なやり方であり、こうした手法を磨き上げる点に、コンテンポラリーダンスの公益性はある。 このような点に公益性を求めなければならないのは、近年、文化助成の考え方が変わったからである。かつて、伝統芸能など「文化遺産」保護、「国民的威信」形成、集客による地域経済波及、芸術体験による教養向上、「前衛芸術」による社会批判機能などを目指した「芸術政策(アート・ポリティクス)」だった文化助成だが、文化という概念が、欧米的「高級芸術」から、ひとびとの生活形式やアイデンティティをふくむ多元的なものに拡張した結果、むしろ「文化政策(カルチュラル・ポリティクス)」の一環とされ、多様な地方文化やアマチュアの活動をもカバーする、福祉サービスのひとつと考えられるようになった。 一方、ピナ・バウシュやコンドルズに見られるとおり、コンテンポラリーダンスにおいては、第一に、セリフや映像、楽器演奏、歌、人形劇など、表現手段に関して「なんでもあり」であり、演者には必ずしもダンステクニックが要求されない。その裏返しとして、第二に、各ダンサーの身体的、人格的な独自性を引き出すことにコンテンポラリーダンスの眼目はあり、作品は各演者のあり方(「実存」)を反映するドキュメントとなる。たとえば、「考えられないときに何を考えるか」など、ひねりのきいた質問を浴びせることによって、各ダンサーの個性を引き出すバウシュの手法はその典型だ。そしてその結果、第三に、コンテンポラリーダンスにおいては、身体的、文化的に多様なもの、異他的なもの同士のあいだに火花が散って「第三の意味」が生まれ、ローカルなものがグローバル化される。ダウン症など、知的障碍者によるユニット「ハンドルズ」を演出した近藤良平の作品は、そのもっとも輝かしい成果だ。コンテンポラリーダンスの作成手法が、一般人や児童を対象とするダンス授業やワークショップに好適なのは当然なのである。 90年代に「ダンスが爆発した」わが国では、2005年、それまで公演数で他を圧倒していたクラシックバレエを、コンテンポラリーダンスのそれが瞬間的に抜き去った。2010年代には、川村美紀子など、コンテンポラリーダンス・ネイティブ世代が台頭しつつある。 だが、国や自治体などにおける予算や文化戦略の欠如など、コンテンポラリーダンスを取り巻く状況は厳しい。先の都知事選において、景気や防災政策に期待する有権者が40%以上だったに対して、文化政策に期待したのは2%にすぎなかった。限られた税収から、福祉や教育、経済対策などの分を削って「文化」、しかもコンテンポラリーダンスに予算をまわすことがなぜ必要なのか、コンテンポラリーダンス・ファンでもない行政関係者を説得しなければならないのである。 コンテンポラリーダンスの手法は、作品作成や上演のためのたゆまぬイノベーションから開発された。現在、月間舞踊公演数は、首都圏で2000件だが、ヨーロッパでは2万件である。一見すると、日本はヨーロッパに大幅に立ち後れているようにみえるが、首都圏の1300万、ヨーロッパ全体の3億という人口比で見ると、むしろ首都圏の方が人口比密度においてはまさっている。 バニョレフェスティバルのミュンヘンプラットフォームディレクター、ヴァルター・ホインによれば、コンテンポラリーダンスを助成することがいかに「セクシー」であるかを政治家が納得することが助成金獲得する「こつ」である。そのためには、あらゆる回路を利用しなければならない。 |