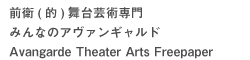10連休といわれた2019年5月の大型連休。日暮里・d-倉庫では「現代劇作家シリーズ」第9弾として、劇作家の戯曲に代わり日本国憲法を題材にした「〈日本国憲法〉を上演する」が開催された。演劇、ダンス、パフォーマンス・アートなど様々な表現方法による参加9団体のうち4団体の舞台を観劇。いずれも意味のまとまりとしての日本国憲法条文は舞台上になかったにもかかわらず、憲法を取り巻く現状が伝わってきた。

IDIOT SAVANT theater company
京都出身のSuper D『新日本帝国』は、やわらかい関西弁と個人への抑圧や強制に響く憲法の強い言葉遣い「シテハナラナイ」「サレナケレバナラナイ」が対照的。議会での不毛なやりとりと決議のあっけなさを戯画的に描き、「ひとまず変えてみたらいいやん」が信条かと思いきや、アブグレイブ刑務所かアウシュヴィッツを彷彿とさせる人間ピラミッドを象徴的に見せるラスト。なかなかに皮肉の聞いた舞台であった。
IDIOT SAVANT theater company 『忠恕。放る。線上。』は、今年2月のTPAMフリンジ参加作品『日本国憲法』の続編。2面の壁に投影されていた日英の憲法条文がなくなり、黒いスーツに身を包みつぶれた声で叫び呻く身体に〈日本国憲法〉への怒りとも祈りともつかない思いが仮託される。しかし2月の『日本国憲法』を見ていない観客に憲法とのつながりが伝わったかには疑問が残った。

中野坂上デーモンズ
中野坂上デーモンズの憂鬱『No.12』は、部活女子高生の世界観を通して〈日本国憲法〉を現出。憲法とそれを取り巻く現代社会の縮図として、校則と先輩後輩の序列社会、女子高生同士のかみ合わない会話が散りばめられる。他者の声など耳にはいらない叫びっぱなしの女子高生。自ら醜態を晒すことで規則を守る意味を伝えられない教師や母ら〈大人〉。国際社会などの外部は宇宙人レベルだろう。読まれることがない校則同様に矮小化された〈日本国憲法〉は、認識外の距離感にもかかわらず纏わりつく煩わしいものとして示される。賑やかで元気いっぱいな舞台には、ひりつくような寂しさも感じられた。

bug-depayse
上記3作品がどちらかといえば憲法への負のイメージを見せるのに対し、bug-depayse 『彼について知っている僅かな事柄』は、それでも憲法が日常を支えることを示す。電動車椅子で登場する〈彼〉が、憲法条文を意味の連なりにならない声で持てる力を振り絞り語る。「第11条」「第12条」と読み上げるガイド役の女性の声で、それが基本的人権条項であることに気づく。小さな体で舞台のあちこちに置かれた自転車のタイヤを回しながら、人生を語る年老いた別の車椅子の〈彼〉の面倒をかいがいしくみる、もうひとりの〈彼〉。何の意味もないように思えるタイヤを回す行為が、日常の営みに見えてくる。〈日常〉を生きることの難しさと大切さが、ハンディキャップを抱える〈彼〉たちの存在感をと共に憲法のイメージに重なる。憲法を理性的思考でとらえることを静かに語り掛けてくる舞台である。
個々の舞台の憲法への距離感だけを言えば共感できるものはなかったが、身近な等身大のものとして憲法が考えられた作品を連続してみることで、憲法を取り巻く現状を改めて考える契機となった。連休中は笠井叡『日本国憲法を踊る』(4/21愛知県芸術劇場小ホール)、かもめマシーン『俺が代』(4/19-4/20愛知県芸術劇場小ホール、4/27-4/30早稲田小劇場どらま館、5/5-5/6沖縄・アトリエ銘苅ベース)、原マスミ×山田せつ子『朗読で聴く日本国憲法』(5/3 三鷹・SCOOL)、秋田雨雀・土方与志記念青年劇場『みすてられた島』(5/8~愛知・知多市勤労文化会館ほか32カ所)など、各地で〈日本国憲法〉が上演された。大型連休を構成する国民の祝日のひとつに<憲法記念日>が含まれることを知らぬ風情にあふれる行楽情報の中、小さなメディアである舞台に日常としての政治を考える可能性があったことを好ましく思う。
|