 |
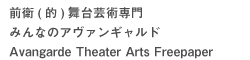 |
|
現在、「artissue」は編集部の自費のみで運営・発行しています。まだ始まったばかりで試行錯誤の段階ですが、応援して下さる皆様からのカンパをお願い致します。集まったカンパは今後の運営資金として大切に使わせて頂きます。 これからも「前衛」の魅力について多くの方に紹介していきたいと思っています。いくらでも構いませんのでご支援のほど宜しくお願い致します。誌面広告も募集しています。 ・振込先: 郵便振替 00130-9-359857「artissue」 ※備考欄にカンパとご明記下さい。 ・他行からの振込 ゆうちょ銀行 019 当座 0359857 |
新野守広 演劇批評家
|
||||
 21世紀の私たちの時代も、20世紀初頭の歴史的アヴァンギャルドたちが体験したのと同じように、秩序崩壊の時代である。100年以上も前の時代に人々に崩壊を告げ知らせたのは、世界戦争と革命の予兆だった。事実、第一次世界大戦が勃発して各地で暴動が起こり、新しい社会秩序が打ち立てられた。一方『ハムレットマシーン』の描く暴動は、第二次世界大戦後の1953年に起こった東独全土での労働者蜂起をモデルにしている。この蜂起が鎮圧された後に出来上がった社会主義国は、前衛の可能性の芽を摘んだ。自我の分裂が消され、反省意識が奪われ、人はマシーンになる。前衛は根絶やしにされ、あとに残されたものは深海で待ち焦がれることだけとなった。 ところが、こうして前衛の死を描く『ハムレットマシーン』が、先王の亡霊が王子の心を支配し、登場人物の多くが次々に殺される『ハムレット』からの本歌取りで作られたことほど、演劇人の心を躍らせるものはない。『ハムレットマシーン』の魅力の一端は、400年も前にシェイクスピアが描いた死の世界を20世紀後半の現実を描く礎石としたところにあるだろう。そして、今から40年も前に前衛の死を描いた『ハムレットマシーン』が、内戦や大量虐殺、自然災害、過酷な労働などで多くの死に直面する現在の私たちの前衛的舞台への思いを勇気づけるとすれば、なんとも皮肉な本歌取りではないか。 葬儀として執り行うか、パロディーとして執り行うか、別の文脈に置き替えるか。2018年4月、東京の日暮里d-倉庫で取り組んだ10団体の舞台は興味深かった。 まず、『ハムレットマシーン』を盛大な葬儀として上演したのは、「IDIOTSAVANTtheater company」である。この劇団は身体を酷使するパフォーマンスを特徴としている。開演すると客席から見て左手にたたずむ女性が第1場のモノローグ(「私はハムレットだった…」)を語り出す。苦しそうに悶えながら金槌を振り回し、後方に立つ数名を殴り倒す内破の所作を踊る女性のハムレット役者。そして第2場(「私はオフィーリア…」)、第3場(「私は女になりたい…」)と進むにつれて、それぞれの場面はソロ、デュオ、集団で踊られ、下着姿になった男性と女性が衣装を交換したり、赤いパラソルを持ち激しく踊った女性が男たちと群舞したり、「カーカカッカ」とでも叫んでいるのだろうか、まるでカラスのような鳴き声を叫んで飛び跳ねる黒い服の男女が乱舞したりと、原作の各場面を身体を駆使して踊っていく。 公演中に3台の大きな液晶モニターを舞台後方の天井に吊るしたり(ここには毛沢東やトランプなどの姿が映った。このうちの1台は幕切れで床に落下して大音響を立て、観客の度肝を抜いた)、舞台後方の赤い冷蔵庫から取り出したドリンク飲料を飲んだりするなど、パフォーマーの身体とともに小道具の存在感が強調されていたのも興味深かった。  ©hideo kobayashi とくに第4幕の暴動の場面は印象に残った。紐で四肢を結び合った10名弱の男女が入り乱れながらも、紐を張った状態を維持しつつ、狭い舞台を縦横無尽に飛び跳ね回る。その結果、中央にいる一人の女性が、原作第5場の「包帯で巻き」つけられたエレクトラになるのである。この紐は、舞台の左右の壁に立てかけてある何本もの大きな木の板に結わえられた。黒い服を着たパフォーマーたちが白い骨壺らしき小道具を持ち、この木の板に文字を書くというパフォーマンスが入ったことを思えば、観客の目の前で死者に捧げる儀式が行われたと考えてもよいだろう。 「IDIOTSAVANT」は震災で亡くなった東北の死者に捧げる舞台も生み出している(『手で触れられるくらいの鈍い空と 遠くに聴こえる潮音を哀しみが示すのならば かもめの眼ざしが飛びつかれてしまうまで 海が泣きだすなんて知らなかったんだ』2016年2月24日~28日、d-倉庫)。『ハムレットマシーン』は、これまでの彼らのやり方を踏まえた上での、前衛の死者に捧げられた儀式であると思えた。このカンパニーにとって死は時空を超えた大きなテーマであることが感じられた。 『ハムレットマシーン』は、『ハムレット』を上演するためにミュラーが原作を翻案したのを契機に書かれたという背景がある。この二つのテキストそれぞれの魅力を思えば、両者を組み合わせて演劇的な効果を試そうと考える団体があるのも当然だろう。  引用された『ハムレット』は、王妃の部屋を訪れたハムレットが母の心変わりをなじるうちに父の亡霊を見て狂気に陥る第3幕第4場に限られていたと思う。この場面はハムレット役とガートルード役の男女パフォーマーが性愛の所作をすることで始まった。二人の動きは次第に激さを増し、最後にはレスリングにも似た汗みどろの大格闘になる。しかも二人の格闘は、詩人が『ハムレットマシーン』第4場の暴動の場面(「不穏な十月に…」)を語り出すとき、きわめて激しい肉弾戦になるのだ。二人の身体能力の高さは驚くべきものだった。 ミュラーが描く労働者蜂起とその帰結としてのマシーン化が、母子の近親相姦の身体パフォーマンスと並置されたことは興味深かった。これに続く第5場では、詩人が「こちらはエレクトラ…」の朗読を始めると、敗戦を告げる昭和天皇の玉音放送が流れ、「ヨーロッパの廃墟」が敗戦直後の日本につながる。おそらく作り手は日本社会の右傾化を念頭に置いて、現在に連続する第5場の「深海」に敗戦直後の廃墟の日本を重ねたのだろう。  『ハムレットマシーン』を日本の戦後史に丁寧に置き換えてみせたのは、「身体の景色」である。開演直後の舞台には、洋装の女性と床に横たわる男性がいるが、女性はすぐに去り、入れ替わりに、自分は大日本帝国の従軍作家だったと名乗る和服姿の男性が入って来る。彼は自殺した妻の声をテープレコーダーで聞き、戦争の記憶をたどるのだという。 私は鈴木忠志演出の『シラノ・ド・ベルジュラック』(2006年11月、新国立劇場)を思い出した。鈴木の演出では日本人男性喬三の存在がメタレベルの外枠になり、彼の見るまぼろしが劇中劇『シラノ』として演じられる。「身体の景色」の舞台に登場した和服姿の作家も、鈴木演出の『シラノ』と同様、劇中劇を導入するための枠であろう。作家が自己紹介を終えると、ハムレット役者の男性が「私はハムレットだった…」と語り出して『ハムレットマシーン』が始まる。しかし台詞は細かく書き直されたり加筆されたりしており、舞台は敗戦直後の日本に置き換えられている。玉音放送が聞こえ、「東京ブギウギ」を踊る女性たちがハムレット役者の男性に迫るのも、戦後の世相を連想させた。 全体的に第2次大戦後の廃墟から60年安保闘争、あるいは68年学園闘争にかけての日本を示す意図が強く出ていた。もちろん舞台は、日本戦後史のおさらいではない。父王の亡霊はイデオロギーを信じた世代の死を示し、女性たちは歴史という娼婦を表していることが見て取れる。こうした男性と女性の役割の逆転を暗示しようとしたのだろうか、第4場の暴動後、自虐的に内向する男性の内面を、一人の女性がいわばメタレベルの枠から語るように演出されている場面が印象に残った。第5場「こちらはエレクトラ…」がテープレコーダーから聞こえてくるとき、冒頭の洋装の女性は舞台奥からゆっくりと現れ、舞台前方まで来て倒れる。しかし彼女は再び立ち上がり、何気ない様子でハムレット役者の男性に近づいた後、もう一度倒れ、幕切れとなった。ここには「世界を回収する」女性が男性とは別の歴史を語り出す可能性が賭けられているようにも思えた。その賭けの行く末を彼らは「激しく待ち焦がれながら」幻視しようとしているのかもしれない。  この後『ハムレットマシーン』が始まる。列車から降りたハムレット役者の男性を一人の女性が出迎える。公演予定のなかった男性は怪訝な様子で劇場へ案内されるが、途中、何かのきっかけで『ハムレットマシーン』の第1場を演じ出す。国葬の場面が終ると、休憩ですとの声がかかり、彼らがいるのが稽古場であることがわかる。こうして演じられていく『ハムレットマシーン』は日常の言葉遣いに書き直され、人物も新たに設定し直されているため、「交換可能」「幽霊」「ママ」「処女」などの言葉が聞こえてくるのを頼りに、今どのあたりを演じているのだろうかと推測しながら舞台を見た。柔らかい曲調の音楽が流れる中、彼らの演じる『ハムレットマシーン』は、いつしか現代の自分探しと重なる。今はハイナー・ミュラーの生きた時代とは別の時代なのだ。俳優たちが「もう暴動は起こらない。嫌悪は隠され、孤独になるための想像力は奪われた」と言うとき、二つの時代の違いは決定的となる。今はマシーン化された状況は同じだが、暴動の記憶は忘却されている。唯一この状況に抗するように、ハムレット役者の男性は「そうではない」と叫ぶが、彼の声は行き場を失ってさまよう印象があった。 『ハムレットマシーン』は終わる。冒頭の女性が再び現れて、スマホで会話をする。妊娠した子どもを堕ろす話になり、彼女は「深海」と言いながら涙を流す。硬質な前衛劇を劇中劇として柔らかく演じた後に、涙という共感の外枠を嵌めた「楽園王」は、状況を相対化するすべを失った人々が、その日常のなかにあっても、『ハムレットマシーン』の言葉を保ち続ける可能性を示そうとしたのではないだろうか。 普段の言葉遣いを駆使して『ハムレット』と『ハムレットマシーン』を組み合わせるやり方は、「隣屋」にも共通していた。『ハムレットマシーン』を軸に他のテキストや創作した会話、ダンスが組み合わされて構成された彼らの舞台では、男女のパフォーマーの対話を通してミュラーとシェイクスピアがつながり、そこに女性ダンサーが絡んだ。 小さな照明が円形に置かれた舞台に、色とりどりの風船が紐で床に結ばれ、人間の背丈ほどの高さに浮いている。そこに男女のパフォーマーが現れ、『ハムレット』最後の決闘の場面を自由な翻案で語り出す。その後、やはり自由な口調で『ハムレットマシーン』が語られるが、たとえば『ハムレットマシーン』の母子の近親相姦を暗示する台詞の後に『ハムレット』の王妃と王子の台詞が語られるという風に、それぞれのテキストは両者の相互関連を重視する形で演じられた。  「7度」の舞台は、独自の視覚的・聴覚的集中度を生み出すパフォーマンスが印象的だった。原色鮮やかなパラソルの下に白いドレスを着た女性が立っている。他には、ビーチチェアと飲み物と小さな造花が見える。そこにスキューバダイビングのスーツにカラフルな上着を着たもう一人の女性が駆け込んできて、「ボーダンガラース」と声を伸ばして発声する。これにパラソルの女性も呼応するため、二人の声が交互に絡み出す。ダイビングスーツの女性は「ボーダン、ボーダン」と言い続けながら、しばらく全力疾走で舞台をぐるぐる回る。その後彼女はビーチチェアに座り、ストローで飲み物を飲んでくつろぐ。  ©bozzo やがてパラソルの女性は、よく響く低い声で、「わたしはハムレットだった」と語りだす。とても丁寧でゆっくりと朗読する彼女の声に耳を傾けているうちに、私は意識が遠くなりかけたが、朗読にこめられた感情の高まりに心が共鳴すると感じられる瞬間もたしかにあった。ビーチチェアに座った女性はデヴィッド・ボウイの『スペース・オディティ』を聴き、その歌詞を朗読する。Webによれば、それは「僕ハブリキ缶ノ回リヲ漂ッテイル/月ノ遥カ彼方ダ/惑星地球ハ青イ/僕ニデキルコトハ何モナイ」という言葉なのだが、なるほど『ハムレットマシーン』の第1場「地球に穴を開け、月まで吹きとばせ」とつながっているのだ。 こうして二人の女性は、それぞれ独特のリズムを最後まで守りながら、主にテキストの重要なキーワードをゆっくりと声に出して朗読し続け、最後に魚たち、残骸、死体という第5場冒頭のト書きを発声した。ここでビーチチェアに座る女性の顔に照明が当たり、公演は終わった。チェアの傍らに置かれた花の花弁が彼女たちの声の振動で左右に揺れたように思えたが、これは私の目の錯覚だったかもしれない。引き延ばされた時間は視覚・聴覚の集中度を高め、エネルギーの流れを生む。ロバート・ウィルソンやヤン・ファーブルが70年代から80年代にかけて試みた儀式的な舞台が思い出された。ミュラーはウィルソンを評価しており、何度も一緒に舞台作りに関わったことが知られている。 素材がミュラーだろうがオペラだろうが、すべて独自の表層的なイメージに還元してしまうと否定的に評されることの多いウィルソンだが、あらすじや物語に沿って登場人物が行動する劇文学の演劇とは異なり、緩慢な動きを通して記号の類似性と反復に意識を集中させ、固定可能なものをグラデーションへ変える変容の演劇を生み出した功績は大きい(レーマン『ポストドラマ演劇』103頁)。「7度」の舞台で何度も繰り返された「ボーダンガラース」という声の響きはまだ耳に残っている。彼らは、音声という空気の振動を利用して感情の振動を生み出そうと試みたようにも思えた。 一方、「風触異人街」の舞台における声は、当日配布のチラシに「声は単なる重層化し、空間に拡散させる装置として使用した」(こしばきこう)とある通り、装置として使われていた。誰かがまず「私はハムレットだった」と声を出すと、複数のパフォーマーが同じ言葉を復唱する。ハムレットの部分がオフィーリアやエレクトラに交換されたり、肯定文が否定文になったりするが、「私は~」という基本形が何度も繰り返されて拡散されるのが印象に残った。  やがて、中央奥のスクリーン手前に大きな箱が置かれただけの舞台に2人のハムレットと5人のオフィーリアが現れ、徐々に客席に向かって整然と歩み寄りながら、「私はハムレットだった…」と語り出す。その後オフィーリアはさらに増え、パフォーマー全体の数も増えて10人をはるかに超える。彼らが同時多発的に行ったさまざまな動きやダンスを十全に理解できたかどうか心もとないが、いくつか原作にない言葉が発せられたとはいえ、全体はほぼ原作通りに演じられ、さらに決定的な言葉は何度も繰り返して発声されたと思う。 たとえば「私はマシーンになりたい」がそうだ。第4場の暴動の場面で多くのパフォーマーが一斉に四股を踏むような動作を行い、狭い劇場全体が地響きに似た振動で揺れるが、その高揚感が減衰すると、「私はマシーンになりたい」という言葉が聞こえてくる。第5場に入り、床に横たわるミイラになった女性を多数のパフォーマーが囲む中、彼女は手にマイクロフォンを持ち、「こちらはエレクトラ…」を終わりまで語る。そして最後にもう一度、「私はマシーンになりたい」と発声すると、スクリーンにミサイルや桜(福島の浜通りだろうか)の映像が映る。先述した客席の男がタイプライターを打ち、赤い腕章の女性が頭に斧が刺さった姿を見せて現れ、暗転。亡霊は私たちの周囲をこれからも彷徨し続ける印象を残して幕切れとなった。  ©玉内公一 「ダンスの犬」の舞台では、ジェンダーがテーマになっていた。開演すると、青いキャップをかぶりスカートをはき大きな乳房をぶら下げるといういでたちの女性ダンサー5人がゆっくり舞台を駆け始める。足にはやや長めの紐でコーラのペットボトルが結びつけられているため、彼女たちが時計回りに舞台上を回り出すと、ペットボトルを結ぶ紐同士が絡まったりする。この公演には言葉はない。床の上で足上げをするなど、さまざまな動きを行う彼女たちを見て、『ハムレットマシーン』のどの場面を踊っているのだろうと想像しながら舞台を見ることになった。 2002年に公開されたアルモドバル監督『トーク・トゥ・ハー』という映画がある。昏睡状態に陥った二人女性と、彼女たちをそれぞれ看護する二人の男性を描いた映画だが、その映画では『縮みゆく男』という劇中映画が上映された。この劇中映画の最後に、身長が極端に縮んだ男が大きな女性器の中に入っていく場面がある。「ダンスの犬」の舞台では、左手奥に人が立って通れる大きさの女性器の模型が置かれ、5人の女性ダンサーが一人ずつこの中に入る。そして通り抜けて出てくると、舞台一面に広がって踊り、暗転。幕切れとなった。 ダンサーたちがこの模型に入るときには森進一の『おふくろさん』が流れ、出てくるときにはチャック・ベリーの『ジョニー・B. グッド』がかかったと思う。こうした選曲も相まって、「女たちの穴は縫って閉じてしまうといい」「彼女の乳房はバラの苗床で、子宮はヘビの穴」「女の胎は一方通行路ではない」「私の産んだ世界を回収します」という男性視線からの生真面目な言葉からユーモアも生まれたと感じた。  ©聡明堂 数組の男女が登場する。男性は何も身に着けていない。女性は男性の股間に後ろから手を入れて、男性器をつかんで入ってくる。男性の行動が女性の支配下にあることを示す滑稽な絵柄だ。実際、男性が「私はハムレットだった…」と語り出すと、女性の手の平の握り方次第で、力が抜けて声が消えたり、再び声が出たりする。しばらくするとダンス曲にのせてチアダンスが踊られたり、リーダーに活を入れられたり、女性たちの男定めの雑談が交わされたり、全員参加の組体操や騎馬戦に似たポーズが取られたりなど、ほぼ体育会のパロディーと化す。もちろん『ハムレットマシーン』や『ハムレット』の台詞の朗読もあり、表面的にはミュラーやシェイクスピアのテキストと絡む会話が行われてはいたが、体操の身体をパロディーとして見せる以上の身体性を提示していたかどうか、やや疑問にも感じた。 ただ、もしハイナー・ミュラーが生きていたら、初期型の舞台を見て喜んだかもしれない。ミュラーは生真面目に受け取られることの多い自身のテキストから笑いが生まれる舞台に興味を示したからだ。たとえばフランク・カストルフ演出『ペンション・シェラー/戦い』(1994年、ベルリン・フォルクスビューネ)がその例だが、一方、そのカストルフ演出でも笑劇の定番である『ペンション・シェラー』はナチス台頭前夜のベルリンに時代を移され、そこに敗戦直後のベルリンを描いた『戦い』が組み合わされるという構成だった。ミュラーのテキストをパロディーにするには、ベルリンの政治性はあまりにも生々しかった。  ©Lee Do-hui 韓国は今も昔も民主主義の実現に向けて人々が熱く語り合う国である。一方、日本社会は保守化が進み、右傾化が著しい。シム氏は公演当日に配布された「出演団体の演出ノート」に次のように書いている-「『機械』を超えて完璧な『無』を夢見る『ハムレット』は、長く伸びた先のとある破壊の地点におり、私たちはそれを観客と共に眺め、彼が不存在に向かっていく様を嘲笑し証明しなければならない。天皇の人間宣言を経て民主主義の国へ。それがなぜいま教育勅語(天皇のために死ね、忠実な臣民たれ)の学校現場での朗読を文科副大臣が『問題なし』と答弁する国になったのか、事態はまさに氏がとぼけた笑いとともに描き続けてきた不条理演劇のそれではないか。いったいこれはどういう社会だ」。シム氏にとって『ハムレットマシーン』は、マシーンになりたいとつぶやく男を観客と共に眺め、「嘲笑し」、民主主義の国を実現することを「証明」するためある。民主主義の実現を目指すことによって、『ハムレットマシーン』に引導を渡そうというのだ。 開演後、大音響ととともに舞台に現れたシム氏は、「こんにちは」「あつい」「ここはどこ、ここ、ここ」などと気楽に日本語で客席に向かって語り掛け、観客とのコミュニケーションを取る。顔を白く塗り白い衣服を着たハムレットとオフィーリアが登場し、『ハムレットマシーン』を演じる中、途中で犬のような姿勢で現れたシム氏は、最後にもう一度登場して、第5場を見守る。こうして見守ることで、かつて自分が「マシーンになりたい」とつぶやく男を演じ、90年代の韓国演劇に大きな衝撃を与えた事実を自らの手で歴史化するとともに、この事実を韓国の若い世代の俳優たちに伝える姿を自己言及的に舞台化しているように見えた。 今、必要なのは、前衛的舞台に熱を上げることではない。韓国社会の民主化を通して『ハムレットマシーン』の賞味期限が切れたことを示すことが重要なのだ。民主主義が根付くとき、『ハムレットマシーン』は古典になる。そのとき、かつて『ハムレットマシーン』に主演した自分自身の過去も死ぬ。シム氏の舞台は彼自身の葬儀にも思えた。 私自身はもちろんのこと、誰がシム氏ほど潔く民主主義への思いを語れるだろう。d-倉庫に集まった人々の前衛的舞台へ賭ける思いには、民主主義を批判する感情が流れてはいないだろうか。 前衛的舞台の源流であるダダイストら20世紀初頭ヨーロッパの歴史的アヴァンギャルドたちは、理性や合理性にもとづく文明を徹底的に批判した。民主主義も彼らによって批判された文明の産物だった。歴史的アヴァンギャルドたちは、西欧近代の外部に立っていた。社会主義や共産主義が現実的な外部にもなっていた。 一方、70年代後半にミュラーが「マシーン」化を描いたとき、社会主義社会はもとより民主主義社会のマシーン化も含意されていた。『ハムレットマシーン』が西側諸国や日本で注目されたのも、このテキストが社会体制の違いを超えて、社会を外部から批判する前衛の立脚点が社会から失われた事態を描いたと受け取られたからだった。「マシーン」化とは、極限すれば、世界を批判するために必要な外部を自ら創り出す力が人々から失われたことを意味する。こうしたテキストを書いたミュラーがロバート・ウィルソンの初期の舞台作りに協力することができたのも、ウィルソンの舞台が記号秩序の変容を通して外部へ向かう想像力を喚起できたからだった。外部などどこにもないが、外部の存在を想像的に喚起することはできる。この可能性へ賭ける期待が日本における前衛的舞台への思いを持続させてきた要因の一つであるように思う。 しかしシム氏にとって、民主主義はミュラーのテキストの外部にある。民主主義社会の実現こそが、人間のマシーン化を描いた『ハムレットマシーン』の賞味期限切れを証明することになるのだ。「劇団シアターゼロ」の公演が投げかけた問いはシンプルだが、西欧近代との同時代的連続性に前衛の根拠を置いてきた近現代の日本には避けて通れない重みがある。その問いかけを言い換えれば、次のようになるだろうか。東アジアに民主主義が根付くとき、19世紀後半以来西欧社会との連続性を仮構し続けてきた日本の近現代は、前衛的志向も含めて、いったん過去のものになる、その先に来るものを見よ、と。
|
||||