 |
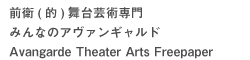 |
|
現在、「artissue」は編集部の自費のみで運営・発行しています。まだ始まったばかりで試行錯誤の段階ですが、応援して下さる皆様からのカンパをお願い致します。集まったカンパは今後の運営資金として大切に使わせて頂きます。 これからも「前衛」の魅力について多くの方に紹介していきたいと思っています。いくらでも構いませんのでご支援のほど宜しくお願い致します。誌面広告も募集しています。 ・振込先: 郵便振替 00130-9-359857「artissue」 ※備考欄にカンパとご明記下さい。 ・他行からの振込 ゆうちょ銀行 019 当座 0359857 |
北里義之 音楽・舞踊批評
|
||||
 三東瑠璃 with Co.Ruri Mito『住処』©bozzo ダブルビル公演のうち、デュオで踊られた『Freestyle』にも触れておくことにしよう。こちらはタイトルから想像されるように、クロールや平泳ぎ、ジャンプ競技やシンクロナイズド・スイミングなど、水泳で見ることのできるさまざまな形や動きを、誇張したり、組み換えたりして再構成した遊び感覚あふれる作品だった。ステージには白線でプールのコースを模した枠が三つならんで描かれ、ダンサーふたりも、マリンブルーのスイミングキャップ、赤と黄のあざやかさが対照的な上着、おそろいの黒の短パンと、色彩感覚あふれる衣装で登場した。水泳中の設定なのだろう、公演の前半は、顔を水につけた格好で観客になるべく顔を見せないよう前屈しながらユニゾンを中心に踊っていき、後半は、それぞれの動きを交互にかわしながらダンスを対話的に展開していくというものだった。全体をポップな明るさがおおっていて、水泳競技をモデルにした両者の関係もゲーム的、息継ぎする呼吸音をサンプリングして音楽に使ったところにも演出の徹底を感じさせた。  三東瑠璃 with Rita Gobi『Freestyle』©bozzo 両作品を支える身体性には、アスレチックでアクロバット的という共通点がある。私たちの場合、時期的に東京オリンピックの開催が影響していることは間違いないだろうが、身体表現の他領域に進出していき、そこをコンテンポラリー化するという現代ダンスの新傾向なのか、最近になってスポーツの身体性をテーマにするダンス公演が一気に増えてきたように感じられる。特に『Freestyle』のほうは、一般的にコンテンポラリーダンスの特徴とされるもの──拡散し多様化するダンスの現在形を意識した作品といってもいいだろう。水泳競技をモデルにしたGobi作品では、身体を空間的にインスタレーションするところから一歩を踏み出し、動きによって自他の関係性を描こうとするとき、ダンスのアスレチックな性格が前面に出てくるようだった。もうひとつの重要な要素は、『Freestyle』でダンサーたちが手足を速く動かすとき、まるで昆虫のように見える動きがあらわれていたことである。結果的に、これが水泳競技を異化する、その意味ではまさにダンス的な役割を果たしていた。昆虫ぶりに取り組んでいるダンサーといえば、OrganWorksの平原慎太郎やブッシュマンの黒須育海などがすぐに連想されるが、昆虫の動きとアスレチックな動きは、ともに機械的になれるという点で相性がいいのかもしれない。 『住処』の出演メンバーには日によって多少の異同があり、私の観劇した8月5日(日)マチネには、青柳佑希乃、安心院かな(この回のみ)、加賀爪智子、斉藤稚紗冬、中村優希、橋本玲奈、森田裕稀と、総勢7人のメンバーが名をつらねたが、ダンサーの資質を生かすという通常の振付が意図する方向性とは反対に、『住処』の群舞は、そのような身体の固有性を消していくものとして構想されていた。このことは現代ダンスのある傾向を大きくおし進めるものとして高く評価すべきだろう。 公演冒頭に登場したのは、積みあげられて小山のようになった身体の塊だった。照明によって一方向から照らされ、黒々と影になった塊の下部から、いりくんだ他人の脇のアーチをくぐり、一本の手が床のうえをはって伸びたり引っこんだりしている。やがてひとりのダンサーが小山を抜けると、床上を上手へと這い、そこでうつ伏せになった。なにやら動きをしてから、ふたたび人体が積みあがって巣穴のようになったところまで戻ってなかに這いこみ、しばらくしてまた抜け出てくると、今度はもう少し遠くの床まで這ってうつぶせになる。なにか小動物の生態系を長い時間をかけて観察しているような印象だったのだが、冒頭のこの場面は、ひとつの風景を現出させる群舞という振付ヴィジョンを端的に示すものだった。『住処』で特筆すべきは、ダンス・フォーメーションがその背景に幾何学的な図形を想定していないことで、まさにその部分に生命的な動きが宿っていくのだった。後半では、わらわらと一列にならんだメンバーが、ひとりのダンサーを床に落とさないようにしながら、まっすぐうえにあげた足のうえを渡したり、床に這いつくばった背中のうえをダンサーに這わせたりして群舞していく印象的な場面が展開した。 群舞が動物の群棲を思わせる身体の風景を立ちあげていった『住処』は、特別な物語をもつことがないため、演劇的なドラマツルギーが描きにくい作品といえるだろう。三東の振付は、そこでアクロバット的な要素を最大限に生かすものだった。その典型的な一例が、ひとりのダンサーを床に落とさないようにしながら、他のメンバー全員が両脚をまっすぐうえにあげる形で一列になって空中に道を作るというクライマックスの場面である。うえに乗ったダンサーが腹這いで列の先へと進んでいくと、彼女を支えるしんがりのダンサーが列の先頭に移って道をたしていくという動きが反復され、全体的には、輪を描いて進行していく一列が、反時計回りにステージを一周するというシーンだ。ここに見られる動き──複数の身体が一体化しながら場所を創造していくという動きのアクロバット性こそが、伝統的になにがしかの物語を描き出すダンスのクライマックスに相当するものといえるだろう。床に落下することなく、無事ステージを一周しおえたダンサーが、イソギンチャクの触手のようになった脚のうえに腰かけて周囲を見回し、両脇で直立する脚の群れを自分のほうになでると、林立する脚は彼女へとなびき、公演はそこで終幕となった。群棲動物さながらの群舞によって生命の濃密さに迫った『住処』は、ダミアン・ジャレ/名和晃平の『VESSEL』やサッシャ・ヴァルツの『Körper』などにはいりこんでいる抽象思考を周到に迂回していくもので、ダンスと身体のレベルを往還しながら現在進行形でおこなわれているダンスの探究に新たな局面を開くものだった。  黒須育海 with ブッシュマン『よいのみつ』©bozzo 新たな群舞のスタイルを切り開きながら、三東瑠璃とは別の方向性を示して注目されるのが、黒須育海の新カンパニー“ブッシュマン”の活動である。最新作『よいのみつ』に出演した歌川翔太、手塚バウシュ、中村 駿、そして紅一点の金子佑紀からなるダンサーたちは、大東文化大学のモダンダンス部時代から踊ってきた仲間を中心とした「顔の見える関係」が高い結束力を築いており、演出・構成・振付を一手に引き受ける黒須のどんな奇想をも、コンパクトで明快な作品イメージへと結晶させる大きな力となっている。人間的なものを出外れていく動物的なものの異形性を男性身体の密集性と結びつけたカンパニーの特徴は、「一本枯れると全体で枯れる運命共同体型である植物がある。一本一本が全て見えない所で繋がっている。数百年に一度、世代を越え花が一斉に開花した後、これらは一斉に枯れてしまう。枯れても花が種子を残し、やがて月日を経て戻る。ヒトの場合はどうだろうか」(黒須育海)と演出ノート記された『よいのみつ』において生命的なるものをテーマにしたことで、『住処』に最接近する作品となった。  黒須育海 with ブッシュマン『よいのみつ』©bozzo 両作品における最大の相違は、カンパニーのメンバー構成を反映して、『住処』が女性ダンサーたちの同質性を強調する振付で踊られたのに対し、『よいのみつ』が紅一点の女性と男性4人によって踊られたことにある。前者の場合、密集性・凝集性の高い群舞をもって性別を無化しながら、これまでの群舞を出外れていくような群舞を生み出したのに対し、性別を意識した振付をおこなった後者は、動物や昆虫のように四つ足になって素早く床を這うといった相対化をおこないながらも、伝統的なダンスにおけるソロやデュオのフォーメーションをとることで、それらがなおも個体の関係性を踊っていることを示していた。 黒須作品において、男女の性差は重要なものとして扱われている。たとえば、女の背後に立った男が、前に立つ女の目を隠したり(女はすぐにその手を払う)その腹に手を乗せたり(女は時間をずらせて男の手に自分の手を重ねる)する場面があったり、女が男たちを追いかけ、そのうちのひとりの足をつかまえて引きずる場面がはさまれるなど、そこになにがしかの物語の存在を観客に想像させるダンスになっているのだ。ブッシュマンにおいて個が消えていくような身体の密集性・凝集性は、動きのユニゾンも含め、もっぱら男たちの間で起こることになる。四つんばいの姿で一列を作り、前のメンバーの股の間に頭を突っこむというフォーメーションをとることで、まるで一匹のムカデが動いているような集団性を編みあげる特異なダンスは、ブッシュマンならではの集団性を端的に表現する振付になっていて、横浜ダンコレで審査員賞を獲得した『FLESH CUB』(2017年1月、横浜赤レンガ倉庫1号館)で、この人間ムカデが一列を組んだり崩したりして集団性を遊ぶさまは強烈に記憶に残っている。 ふたつの作品には重要な相違がもうひとつあり、それはダンスが踊られる環境に関するものである。『よいのみつ』公演ではこれまでにない趣向が用意され、観客たちは、セッションハウスの階段をステージのある地階に降りるところから、足元の暗いなか、まるで遊園地のお化け屋敷に入るようにして、周囲をインスタレーションされた竹群に囲まれながら下っていくことになっていた。割った竹を壁に沿って立て回した会場は、上手下手に吊りさがる灯籠の薄あかりでぼんやりと照らされるという、すでにして異界のしつらえのなかにあり、あたりにかすかなスモークが立ちこめるなか、虫の音に導かれるようにして席に着くのであった。昆虫か動物か、なにかしらの生物が群棲する巣穴に侵入していく塩梅であった。 こうした『よいのみつ』の演出に対し、『住処』の冒頭場面にあらわれたのが、折り重なるダンサーたちの身体が作りあげた塚であり、その肉塚に開いた巣穴から這い出してくる動物だったことを思い出してほしい。三東瑠璃が描き出している世界は、人も動物も、土のような物体も、すべてが身体で織りあがった世界、ある意味で「平面的」といえるような世界なのではないかと思う。身体の外に、なにか環境に相当するようなものが別にあるのではなく、身体そのものが世界を織りあげる生地であるというヴィジョン。そうした表現に女性だけを集めるという身体の同質性は、大きく貢献した。これにくらべると、『よいのみつ』は、環境としてある巣穴のような場所にダンサーたちがやってくる構成をとっている。等しく「生命的なもの」といっても、黒須作品の場合、踊り手の身体は、動物や昆虫の動きによって異化される人間的なるものとして考えられ、ここまでのところ生物の範囲を物質的なものへと逸脱していくというようなことはない。一種の擬態であり、作品の後半になって、紅一点の金子佑紀が手に明かりを掲げて入るのも、動物・昆虫的な集団性を形作る男たちに対して、彼らを異化する個として、すなわち、人間的な要素を持った存在として登場したといえるだろう。 ともに「生」を扱った両作品をくらべてみると、実際に踊られた「生」の表現の間に、振付の背後にあるヴィジョンを、女性身体と男性身体の本質的な相違にまでさかのぼって性格づける、根源的な感覚の違いが横たわっているように思われる。周辺作品をあげていえば、三東瑠璃『住処』にみられる物質への親近性は、下島礼紗率いる“ケダゴロ”が、雑司ヶ谷鬼子母神の境内に特設会場を設営し、雨の降る日も晴れの日も土にまみれて踊り倒した『ケダゴロ』(2016年4月)が、モノだかヒトだかわからなくなるような渾然一体とした物質感をかもしだしていたことと深く通じているだろう。この点、ダンス作品において男性身体が描き出す「物質性」には、たぶんに観念的な要素を感じざるをえない。こうしてみると、女性身体には物質的なるものにダイレクトに接続する感覚の回路があるようだ。解き明かすべき身体の謎のひとつである。 かたや、黒須にとっての動物的なるものを考えるとき、『よいのみつ』公演の少し前、TOKYO SCENE 2018「身体観察」に参加して踊ったソロ作品『魚の目』(2018年7月、六本木ストライプハウス)が参考になると思う。この作品で、黒須は魚に擬態して踊ったのだが、実際のダンス公演であらわれていたのは、人でもない、魚でもない、まして「人魚」や「半魚人」といったキメラでもない不可解な存在がおこなう奇行の数々であった。前代未聞のありえない生物の設定から、彼ならではの奇想が噴出し、ときには暴力的なほど過激なイマジネーションを解き放つ。こうした黒須ワールドのなかの『よいのみつ』は、身体を異化するさまざまな奇想によって、長期間にわたり人間主義的に踊られてきたダンスの歴史に変更を迫ると同時に、私たちの目から周到に隠されている人間関係そのものの暴力性をあばいていくところに本領を発揮するといえそうだ。
|
||||