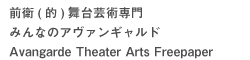野外劇文化の半世紀
梅山いつき 演劇研究者
早稲田大学演劇博物館で現代演劇に関する企画展を手がけた後、現在、近畿大学文芸学部で講師を務める。アングラ演劇のポスター、機関誌をめぐる研究や、野外演劇集団にスポットを当てたフィールドワークを展開している。著書に『アングラ演劇論』(作品社、AICT演劇評論賞受賞)、『60年代演劇再考』(岡室美奈子との共編著、水声社)。 |
1.環境に身を委ねる
先日、縁あって瀬戸内海に浮かぶ周防大島を訪れた。宮本常一の生まれ故郷としても知られる島だ。着いてすぐ自転車を借りて海岸沿いの国道を走り始めたが、思いがけない車の交通量に圧倒されて進路を内陸へと変えた。すると人家が集まっている町はすぐに終わり、そこそこきつい勾配の山道が始まった。そうか、島に暮らす人たちは海と山に挟まれるようにして暮らしているんだな。そう思いながら、山間の農道をひたすら走った。自然の狭間に立たされ、その威力を前にすると、自分がとてもちっぽけな存在に思えてくる。しかし、それは恐れとは異なる感覚で、人なら誰しも身に巣喰う余分な尊大さが祓い落とされ、自分の軸が中心に整ったような清々しいものだ。
この感覚は野外劇の味わいに近い。野外劇は創り手がどんなにがんばって準備しても、野外である限り天候に左右され、台風や大雨のせいで公演中止を余儀なくされる時もある。おもしろいのは、そんな時に上演する側が自然の力を素直に受け入れ、じっと耐えるし、観る側も残念ではあるが、そういうアクシデントも含めて野外劇の存在を認めていることだ。野外で上演することは、自分ではコントロールできない力を創り手に受け入れさせる。見方を変えれば、創り手は上演を成功へと導く最後の一手をあえて手放しているということになるが、それは決してネガティブなことではない。自らの意思を押し通すのではなく、環境に身を委ねることが、舞台を成功させたときに、立ち会った者に人知を超えた力の存在を感じさせ、作品をより豊かなものにするのだ。
野外劇には自分本位な生き方をよしとしない精神性が地下水脈のごとく滔々と流れているのかもしれない。おおげさかもしれないが、野外劇には生き方について考えさせるだけの深淵さがある。それはいずれ消えて無くなってしまうという野外劇のそもそもの在り方にもあらわれている。期間限定で建てられるテントなどの仮設劇場は、生まれた瞬間から消滅へ向かう道を歩み始める。例えば、回り舞台やクレーンを用いた大掛かりな仕掛けと数トンもの水を滝のように落とす「水落とし」で知られる水族館劇場(1987年-)。3階建の建物に匹敵する高さの特設テント劇場は建設現場の足場を使って骨格を組み、テントで全体を覆ったもので、公演期間中であっても、未完成な建設途中の建造物のような印象を受ける。実際、初日の幕が開いた後も舞台の作りこみは継続されるし、そうこうしているうちに楽日を迎えてしまう。つまり、水族館劇場のテントとは舞台の幕が開いた後も成長を遂げる「未完の建造物」であり、同時に朽ちていく「廃墟」でもあるのだ。寺山修司は詩「懐かしのわが家」で自身の肉体を「不完全な死体として生まれ 何十年かかゝって 完全な死体となる」と言い表したが、野外劇もまた、我々人間のように「不完全な死体」としてこの世に生を受けたものなのかもしれない。水族館劇場のように、野外劇には生命の誕生から死までの時間が凝縮されているのだ。
本稿では野外劇のなかでも一時的に仮設劇場などの演劇空間を設えて上演する集団を取り上げ、その特徴や歴史的な流れについてわずかではあるが記したものである。野外劇の魅力をここで紹介した集団だけに集約するのは到底無理である。それでも、おもしろさの一端が少しでも伝わることを願って筆を進める。
2.運動としての野外劇 紅テントと黒テント
野外劇づくりは仮設劇場を建てることのできる場所を確保するところから始まる。規模によっては数カ月ものあいだ、劇団員は敷地に寝泊まりしながら準備をする。たとえ期間限定であっても見知らぬ者が生活し、本番が始まれば不特定多数の人間が出入りすることになるため、野外劇を受け入れる側には覚悟が必要だ。ゆえに新たな受け入れ先を開拓することは容易なことではない。現在、東京であれば新宿の花園神社が野外劇のメッカであるが、今から半世紀近く前に状況劇場の紅テント(1962年-)が花園神社を含む新宿で上演することは、体を張った戦いであった。
そもそも、日本の芸能史を遡れば、歌舞伎だって能だって最初は野外で上演されていた。芸能のルーツは野外にありといっても過言ではない。「芝居」という言葉の通り、大昔は青空のもと人々は芝生の上に座って劇を楽しんでいたのだ。ところが長い年月のなかで芝居は屋内で見るものへと変わっていき、劇場は落ち着いて劇を鑑賞できるけれど、どこか堅苦しい場所へと姿を変えた。1960年代に入って、芝居を志す若者は既存の劇場以外を上演場所に選ぶ。そうさせた原因は劇場のサイズが大きすぎて彼らの身の丈に見合わなかったためであったが、劇場という枠組みに縛られず、「どこだって演劇空間になる」ことを創り手たちに実感させた。
 提供:「写真集 唐組」 提供:「写真集 唐組」
紅テントや演劇センター68/71(1968年-)の黒色テントのような野外劇の出現は、そうした演劇空間の拡張のなかで捉えられる現象である。60年代の紅テントは時に機動隊との衝突を引き起こす事件であり、喧騒の時代を象徴する存在だった。唐十郎たちは街の浄化運動の煽りを受けて新宿を追われた時も決して屈することなく公演を強行し、逮捕者を出すまでになった。そうやって体を張って表現の場を獲得してきたのだ。黒テントも70年代に沖縄で公演の許可取り消しをめぐって裁判を起こしている。この裁判は長期化したのと場所が沖縄だったために経済的に集団を圧迫したが、それでも引かなかったのは、これが一回の公演をめぐる争いを超えた、公有地とはいったい誰のものかを問う戦いだったためである。
1960年代から70年代の紅テントや黒テントは、野外劇に運動としての側面があったことを今日に伝えている。現在ではかつてのような体制側との激しい衝突はないものの、その精神性は後続の世代に受け継がれている。紅テントの系譜には金守珍らの新宿梁山泊(1987年-)や中野敦之らの唐ゼミ☆(2000年-)が続き、それぞれ紫テントと青テントによる野外劇を上演している。一方の黒テントは紅テントのようなはっきりとした系譜を持たない。結成時より集団性を重視していた黒テントは、約半世紀にわたる活動も時代ごとにテーマが異なることもあって、集団について一人の作家に集約して語ることが難しい。だが、黒テントが他に与えた影響は大きい。翠羅臼らの曲馬舘(1972-80年)は「旅・芝居・生活」を標榜しながら全国を旅した集団だった。芝居を運動として展開しようとした点で、70年代に「運動の演劇」を掲げていた黒テントは反面教師的に意識される存在だった。翠たちの目には黒テントの演劇は芸術の範疇にとどまり、運動性に乏しいものに映った。そして曲馬舘は労働者たちの生活のただなかで演劇を成立させ、よりラディカルに体制を批判しようと試みた。曲馬舘と黒テントの関係は新宿梁山泊と紅テントとの関係とは全く違う。だが、批判という形で黒テントの「運動の演劇」と向き合った曲馬舘が、どうそれを乗り越えようとしたのかは十分に検証する必要があるだろう。
 提供:「写真集 唐組」 提供:「写真集 唐組」
3.見えない劇場
―寺山修司の市街劇とPortB『東京ヘテロトピア』
紅テントや黒テントのように、野外劇には規制の枠組みに満足せず、表現の場を新たに切り開こうとする「生み出す力」がある。それは仮設劇場を建てるといった物理的な方法を取らずとも発揮されるものだ。寺山修司の「市街劇」は仮設劇場を構えない野外劇だ。市街劇の試みは1970年の『イエス』に始まり、その後、同年には街全体を劇場化しようとする『人力飛行機ソロモン』が生まれる(両作とも演出・竹永茂生)。『人力飛行機ソロモン』はオランダやフランスなどヨーロッパ諸国でも上演された。街中の路上や広場で俳優たちがチョークで「1メートル四方1時間国家」という劇場をつくり、それは「2メートル四方二時間国家」といった具合に拡大されていき、日没時には街全体が劇場国家へと変貌しているという壮大な試みだった。ここで生まれるもう一つの国家は、現実世界の国家のように国境を持たず、観客の想像力次第で拡大していくのだ。
寺山の市街劇の遺伝子は、時を超え、今日では高山明のPortB(2002年-)の野外劇に受け継がれているように思う。PortBはこれまでに街を舞台にしたツアー型の演劇を何作か発表している。例えば、2013年の『東京ヘテロトピア』は東京に点在する複数の「アジア」をテーマに構成された、観客参加型の作品だ。参加者はガイドブックと携帯ラジオを手に、あらかじめ設けられたチェックポイントへ向かい、ラジオを指定の周波数に合わせると、その場所に縁のある人物やコミュニティーにまつわる物語が聴こえてくる。その物語とは、普段は接点がなければ意識されないコミュニティーや人々の記憶に関するものだ。つまり、本作は“いる”のに“ない”ように思われているものを観客の手で浮かび上がらせるものなのだ。創り手はそのための仕掛けを用意はするが、各スポットに“いる”わけではない。物語はラジオという目には見えない電波に乗ってやってくるのだ。
東京という都市空間には複数のコミュニティーが存在し、多様な文化と生活が存在している。それらは“東京”という空間を共有しているはずなのに、異なるレイヤーに複層化されている。本作を通してPortBがはたした役割とは、そうした位相の生活圏域を同一平面上でつなぎあわせ、さらには過去と現在をもつなぐことといえよう。厳密には、つなぐのは参加者である。参加者はガイドブックとラジオを携えて、水平軸と垂直軸が交差するところに立つのだ。その時、参加者の多くが東京という都市空間が少しだけ拡張したように感じるはずだ。
寺山の市街劇やPortBの取り組みは、物理的な劇場を構えないことが、かえって無限の広がりを観客の想像世界にもたらす、非常にラディカルな野外劇といえるだろう。
4.あやうい時代のロマンス
―犯罪友の会『ことの葉こよみ』
近年ではPortBの試みや、やなぎみわのステージトレーラープロジェクト『日輪の翼』(2014年-)のように新しい野外劇が生まれている。その一方で、歴史ある野外劇集団が活動に終止符を打っている。昨年は維新派が台湾で最終公演を迎え、解散となった。昨年は維新派だけでなく、関西を代表する老舗野外劇集団・犯罪友の会(通称・犯友)が最後の野外劇を上演した年でもあった。最後に犯友の最終野外劇を紹介したい。
犯友は1976年に結成し、作・演出をつとめる武田一度が座長をつとめてきた。これまで大阪を拠点に野外劇と屋内劇の二本柱で活動してきたが、近年では野外劇の頻度は減り、屋内劇へと比重をシフトしつつあった。そして遂に昨年野外劇の方の幕を下ろすことになったのだ。犯友の仮設劇場は丸太を組んで建てられるが、舞台と客席でその組まれ方が異なる。舞台面には屋根がなく、セットが建て込まれている状態で、二階建てのセットが組まれることが多い。一方の客席は階段状に組まれ、庇のような屋根が付いているが、舞台に最も近い平土間のベンチ席部分には屋根がない。よって雨が降ると困ったことになる。昨年の公演は台風接近に伴う悪天候のなか上演された。わたしは辛うじて台風を避けて観劇できたが、観劇中、雨に見舞われた。すると誰が合図を出すまでもなく、当然のように階段席の観客は席をつめて屋根なし席の観客を迎え入れ、皆で体を寄せ合って雨のなか奮闘する役者陣を見守った。劇場空間として完結していない犯友の仮設劇場は、法制度の網の目をかい潜るためのものでもあるが、時に不自由な屋根なし席のように、不足があるからこその豊かなつながりを生み出し、吹き付ける風雨、きしむ木々の音さえも自然を間近に感じさせる開放感に溢れた空間なのだ。
武田が紡ぐ物語も優しさとおおらかさに満ちている。市井の人々に注がれる眼差しは温かで、それを受けてたつ役者たちの明るさも相まって、舞台は大阪らしい優しい笑いに包まれる。この優しい笑いは人々が背負う苦しみに裏打ちされているもので、野外劇最後の作品となった『ことの葉こよみ』にも辛い過去の記憶を断ち切ろうともがく人々が描かれる。物語の時は1964年の東京五輪と七十年の大阪万博の間の頃で、父の代から続く暖簾を守る寿司職人の若者と、そのすぐ近くの料亭の中居との恋を中心に、彼らを取り巻く人々が描かれる。セットや衣装の風合いはノスタルジックな雰囲気を醸し出しているが、それに反して半世紀以上昔の物語に感じさせないのは、2020年の東京五輪を控え、万博招致に躍起になっている大阪府知事の様子にみごとに重なっていたためである。物語に生きる人々は新しい時代の到来を願うものの、五輪が終わった途端に次は万博といって沸き立つ世の風に乗り切れない。戦争の記憶はいまだ薄れておらず、上海から引き上げてきた少女がトラウマに苦しめられる場面も出てくる。過去との折り合いのつけ方に明確な答えが示されるわけではないが、辛い記憶を切り捨てるのではなく、かといって過去にとらわれたままではない生き方が劇中模索されていた。
5.野外劇は文化
本稿で触れた野外劇はほんのわずかだが、それでも、それぞれの仮設劇場の形状や活動の多彩さは伝わったのではないだろうか。犯友の丸太で組まれた仮設劇場を思い出すと、野外劇とはひとつの文化なのだと気づかされる。劇場の形態や組み立て方には集団の思想が反映されているものだ。犯友の劇場は、代々集団内で受け継がれてきた丸太の組み方を知るものでなければ建てるのは困難だ。文化とはそういう身体知に支えられているものなのではないだろうか。思えば、野外劇には劇場の中に入るときに靴を脱いで敷物の上にあがって見るスタイルのところがいくつかあるが、これも野外劇文化のひとつと言えるだろう。以前、とある野外劇で、カバーを靴にかけて、靴は脱がずにシートの上にあがらされて観劇したことがあるが、強烈な違和感をおぼえた。脱がずに済む分楽なはずなのに、敷物の上に靴を脱がずにあがることに抵抗を感じてしまう。この感覚は習慣によるもので、理屈で説明できるものではない。こうした観客の不合理な身体感覚も野外劇文化の一部に違いない。つまり野外劇は創り手や観客の身体知に支えられているものだから、身体知が低下すれば、おのずと文化の方も途絶えていってしまう。聞くところによると、新たに上演場所を開拓するのは年々難しくなっているそうだ。それは社会が複数の価値観や文化が雑多に交じり合いながら共生するような環境を嫌厭するむきにあるためとも考えられ、加えて、わたしたちの身体感覚の変化にもよるものだろう。では、かつての野外劇集団のように、閉塞した都市空間に風穴をあけるような演劇集団は登場するのだろうか?また、今日の観客の身体にはたらきかけるにはどういった手法が有効なのだろうか?野外劇シーンに新たな風が吹くことが期待される。
|