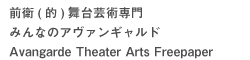©研壁秀俊
一人の男。少しばかり手を広げ、真っ白な、何もない空間を、超低速で、歩く。いや、違う、歩くのではない、もっとも敏感な〈性感帯〉へと皮膚を裏返すようにして、その身体を剥き出しにする。その剥き出しが徐々に観客の温度を、空気の震えを、さざめく環境の生活音を、捉えて感知するフィギュールが、私たちによって〈歩行〉と呼ばれている身体動作と似た何かとして、顕れてくるのである。
私は彼、武本拓也の素性を知らない。この「知らない」というのは二重の意味を含んでいる。第一に、『象を撫でる』のタイトルとフライヤーの文言から別役実の『象』が彫塑したケロイド男と響き合うものを感じ興味を覚えSCOOLへ足を運んだが、彼の経歴を知っていたわけではないということ。第二に、さて上演に接したのちに、およそあらゆる属性が剥ぎ取られてしまいただ〈ある〉ことしか知らない彼の身体から、観客は彼の「素性」を知るすべを何もかも奪われてしまう、ということである。
「歩いている者」とすら名指しえない彼の身体は、どのような「素性」をもたらす属性も宙吊りにして放下してしまう。それは究極的に制度に回収されない〈いま・ここ〉の〈身体〉こそ演劇の本質だとする前衛の特権性を解体する。いまや疑われているのは、現前する〈いま・ここ〉なのだ。
極めて効果的に用いられる照明や音響効果に注目しよう。たとえば、彼が右手の方向へと移動すると、一瞬、幻聴かと思えるほど微かに、風鈴の音が聴こえてくる。可聴域のギリギリに鳴るそれは、「聴こえる音」によりも「聴こえない音」へ観客の注意を差し向ける。余震が続くと、実際に揺れていなくても、揺れを感じてしまうように、〈いま〉に鳴ってはいないが、しかし鳴っているかもしれない音へと観客の知覚が開かれていく。つまり武本の素性の知れない身体は〈いま・ここ〉へ現前する必然的な存在を退け、〈いま・ここ〉に顕れることのない偶然の存在に形象を与えるありえない実験なのである。

©研壁秀俊
〈いま・ここ〉に存在してはいないが、しかし存在しているかもしれない不分明な圏域へと誘い出す武本のパフォーマンスは、メルヴィルが創出したあの類まれなる人物、命令された仕事をむしろ「しないほうがいいのですが」と拒否する書生バートルビーを思い起こさせる。
存在することができるとともに存在しないことができる存在は、第一哲学においては、偶然的なもの、と呼ばれる。バートルビーが冒す実験は、絶対的偶然性 contingentia absoluta の実験である。(アガンベン『バートルビー 偶然性について』)
アガンベンは、バートルビー「むしろしない」の定式に「存在しないこともできる」非の潜勢力を見出した。武本の実践がバートルビーに比肩する絶対的偶然性の実験であるというのは火を見るよりも明らかだ。彼の身体は、わたしたち観客のまなざしが発する「踊れ」の命令に「踊らないほうがいいのですが」と、ただ世界を感受する剥き出しの受動性を顕わにすることで返答するのだから。それは存在することもできたが〈いま・ここ〉には存在することのできなかった、私たちの影を召喚する。
実際に、武本がSCOOLの角へ向かって移動し始めるとき、白い壁には彼の影が映し出される。しかし、この見方はすでに転倒している。影が映し出されるのではない。影が動き、彼が映し出されているのだ。彼はただ身体を剥き出しにしているのであり、何もなしてはいない。〈いま・ここ〉を震わせるのは本震ではなく、余震でもなく、余震の影なのである。そんなことはありえないのだとするならば、それこそただ超スローなテンポで歩く「前衛の影」が一部の観客の嗜好を満たしていたに過ぎなくなる。その時、観客はありえないことを、ただなかったことにするだろう。
だから問われているのは〈いま・ここ〉を必然化する観客のまなざしである。バートルビーは「食事をしないほうがいいのです」と言って静かに事切れた。しかし武本は雄叫びのように産声のように気味の悪い声を発する。バートルビーの定式によれば、むしろ声は出さないほうがいい、声を出さないことのうちに存在することのなかったものの存在が発現する、がしかし、出さないほうがいい声は出てしまう。<いま・ここ>に存在するはずのない、偶々に聞こえてしまった非在の声……この声をいかに聴くのか。あるいは、その<影>を私たちは存在させることができるのか?
|